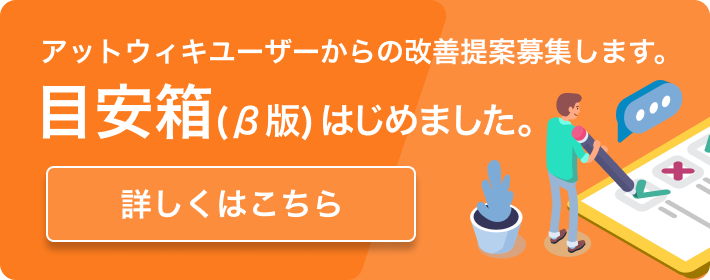「水、流れる。」(2007/01/11 (木) 11:04:56) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
・水、流れる。
小高い丘の上、周りを見渡すと雄大な山並みが見える。雨を吸い込んだ地面からは強い自然の香りが発せられ、都会育ちの俺の鼻を強く刺激する。
「何もないな……」
雨が降っているのも理由の一つかもしれないが、村をぐるっと見渡しても人が歩いている様子はない。それどころか自動車さえも走っていない。
「そんなことないよー」
隣で傘をさした秋音が言う。
「本屋もないしコンビニもない……何があるんだ?」
「静けさなら、あるよ?」
「それを何もないと言うんだ」
何か変なこと言ったかなと主張するように首をかしげる秋音。雨粒がかかったのかぐしぐしと眼鏡をぬぐい、それとともにYシャツの赤いネクタイがゆれる。
「静けさに関係する話なんだけど、今夜はカレーらしいよ?」
「どこにも関係ないな」
「カレー食べるとみんな静まるよ?」
「もともと食事中はしゃべらないもんだ」
「えー、おしゃべりは楽しいのに」
どこかずれている会話。最初に会った時はめんくらったが、もう慣れた。そして村には何もないことがわかった。
「もういいわ。案内ありがとな」
「どういたしまして。それじゃカレー食べに行こう!」
そういって秋音は身をひるがえし、下り道へと足を進めはじめる。赤いスカートが揺れ、ひとつに束ねた髪がぽんぽんはねている。少し歩みを早め、秋音に追いつく。
「とりあえず、だ。まだ昼なんだが」
「昼もカレーだよ?」
「夜は昼の残りってことか……」
「違う違う。夜は夜で作るよ? 皆カレー好きだからねー。お父さんは三杯はいくね!」
「秋音はどのくらいよ?」
「福神漬けなら一パックいけるね! シューヤもどう?」
「俺はそんなにいらないな」
田道修野(たみちしゅうや)、田舎っぽいとよく言われる俺の名前。
正木秋音(まさきあきね)、目の前の少女の名前。年は同じだが、言動から考えると二、三歳下としてもだれも疑わないだろう。
「明日から一日中一緒だねぇ」
「その表現はどうかと思うが、学校案内頼むぞ」
明日から秋音と同じ学校に行く事になる。引っ越しして一番の問題がやはりクラスに溶け込めるかどうかだ。
秋音がいるから溶け込むのも楽かもしれない。
「カレーなくなるよー」
少し考えていたら秋音から離れてしまっていた。全く、どれだけ食べるんだか……
#
丘を降りるとそこには大きな家が二件。
それは両方とも正木家の家だが、片方は俺とオヤジが貸してもらって住んでいる。
オヤジの名前は田道功治(こうじ)。公務員で一応偉い役職についているらしく、この村の開発に関しての話し合いのため俺と一緒に引っ越してきた。
俺一人残ってもよかったのだけれど、仕事はできても家事はさっぱりの父親を一人暮らしにさせるのはどうかと思いついてきた。
特に親しい友人もいなかったから未練は全くなかった。
買い物に行くのにバスで一時間はさすがにキツイけれど。
「おぉ修野、戻ったか。秋音ちゃんもおかえり。俺は話し合いにいってくるからな」
玄関から家に入ると、ちょうど傘を持ったオヤジが家をでるところだった。
「昼飯は食べたか? 秋音が言うにはカレーらしいけど」
「それが相手先の家の昼食に呼ばれていてな、本音を言えば空音さんのカレーはぜひとも食べたかったんだが……」
「空音さんは既婚者だぞ? 狙っても無駄だ」
「あんなに料理がうまくて綺麗な人はそういないぞ? 空音さんが独身だったら俺は絶対お付き合いを申し込んでいたな」
「秋音もいるんだから、滅多な事言うな」
「はっはっは、もちろん冗談だ。おしどり夫婦って言うのか? あんなのを見せつけられちゃ俺の出番はない。そうそう、秋音ちゃんだってもう少ししたら空音さんみたいに綺麗になるんじゃないか? 修野、ツバつけとくなら今のうちだぞ」
「ほっほー、じゃあ私もシューヤにつーばつーけたー」
「うわ! きたねーな! やめろって!」
秋音が自分の指を舐め頬に押し付けてくるのをブロックする。
「それじゃ行ってくる」
「あぁ、いってらっしゃい」
「またねーおじさーん」
「早くお父さんと呼んでくれるようになるのを願ってるよ」
「オヤジ! さっさといけって!」
手を上下に振り追い払う。一旦調子に乗ると止まらないのがオヤジの悪い癖だ。
「お父さんって呼ぶとおじさん喜ぶの?」
「……知らん」
「じゃあ帰ってきたら呼んでみるね!」
「それはやめろ、またややこしくなる。あーカレーの匂いがするな、早く行かないと無くなるぞ?」
シューの話は脱線することが多いし、空音さん達も待っている。俺もそろそろカレーが恋しくなってきたから話を打ち切ろう。
「そーだね、早く行かないと無くなるかもね。お父さん、中に入ろ?」
「な、何言ってんだよ! お父さんとか呼ぶな!」
「あれー、怒られたよ。おじさんの予行練習だったのに」
「……そうだ、怒られるから言うのはやめろ。な?」
「了解しましたー」
まったく、いきなりお父さんとか呼ぶなっての……意味が判ってないだけまだいいけどな。
#
靴を脱いであがり、秋音はまっすぐ台所へ。俺は何も言わずに洗面所へ。
うがい手洗いとすませたところに秋音がやってくる。
「うがい手洗いやってこいって……お母さんはひどいね、目の前にカレー置いてから言うんだよ?」
「秋音が悪い、ちゃっちゃとすませろ」
「私の分もやってよ、丘に登って疲れたよ」
「できるか。って髪濡れてるぞ」
「傘に穴が空いててびっくりしたよ。途中で枝に引っ掛けたとき壊れたのかな?」
「髪を拭くのも追加だ。さっさとしないと俺がカレー食っちまうぞ」
「食べ物の恨みはこわいよ? 報復がいやなら私が手を洗う間に髪拭いて!」
「まだ何もしてないっての……」
仕方なく置いてあったタオルを取り、がしがしと髪を拭く。
「おらおらおら!」
「乱暴にしないでよー」
「修野君、娘に乱暴は駄目だよ?」
いきなり俺たちの背後から現れたのは秋音の父親の俊夫(としお)さん。
これはやばいところを見られたかも……。
「これは乱暴を働いたわけじゃなくてですね、秋音に頼まれてやった事で」
「おとうさん、これは合意の上での行為ってやつですよ」
「違うわ!」
「合意の上ではないとなると、やはり無理やりだったんだね?」
「いや、もう、かんべんして下さい……」
俊夫さんは詰問口調ではなく少し笑い顔、秋音に乗っかって面白がっているだけだ。敗北宣言しないかぎりいくらでも攻められるだろう。
「ほい、手洗い完了だよー」
「もう髪も大丈夫だろ。全く、自分の髪くらい自分で拭けっての」
「修野君は秋音と仲が良いねぇ、僕だって秋音の髪を拭いたことないのに」
「仲が悪いとは言いませんけど、振り回されているだけのような気がします」
「今日は私が振り回される番だったけどねー」
「うらやましい限りだよ。まるで昔の僕とクーを見ているみたいだ」
そういって遠くを見るような仕草をする俊夫さん。
「空音さんと秋音じゃ全然違いますよ」
「それがそうでもないんだよね……まぁそういう話はおいおいしてあげるよ。空音が待ってるし先に行ってて」
「楽しみにしてますね。それじゃ秋音行くぞ」
「はいはいー」
#
居間に入ると食卓には人数分のカレーとポテトサラダが並べられていて、空音さんはもう席についていた。
「すいませんお待たせしました」
「それは構わない、夫もまだ来てないしな。ちゃんと食べる前には手洗いうがいをやってもらわないと、病気でもしたらたまらないからな」
「はぁ……」
この親にして、この子ありといったところか。納得。
「待たせたね、それじゃ頂こうか。いただきます」
俊夫さんに続いて皆いただきますと言い昼食が始まる。
向かって正面に俊夫さん、俺の左に秋音、左正面に空音さんという座席だ。
しばし無言でスプーンと食器がぶつかる音だけ聞こえる。この時ばかりは秋音も何もしゃべらない。
少したって腹の虫も落ち着いたのか、秋音が口を開いた。
「おかあさん、今日はシューヤを丘の上に案内してきたよ」
「ふむ、修野君は村を見てどんな感想を抱いた?」
「そうですね……何もないなぁと。空音さんはずっとこの村に住んでいるんですか?」
「あぁそうだ」
「えっと……とすると、俊夫さんとはどうやって知り合ったんですか?」
「それは僕が説明するよ」
そう言ってスプーンを置く俊夫さん。
「僕がこの村に来たのは本当に偶然だったんだ」
少しはにかみながら話を続ける。
「恥ずかしながら大学生時代に傷心旅行をやっていてね、行くあてもないバイク一人旅さ。快調にとばしていたんだけれど、ちょうどこの家の目の前でスリップして電柱に激突してしまったんだ」
「あの時は凄い音がしたからな、雷が落ちたのかと思ったぞ」
「それで空音に助けてもらって、うん、まぁいろいろあったんだよ」
「君が泣きやむまでずっと頭を撫でてやっていたな……あの夜は忘れられない……」
「い、今言うことじゃないだろ!?」
「何を言う、大切な思い出だ。今でも鮮明に思い出せるぞ? そうあの日は……」
空音さんが独演会を開こうとした時、俺は俊夫さんからの(タスケテ)というコールを受信した。
「えーと! 空音さんはずっと村に居て俊夫さんがこなかったらとか考えませんでしたか?」
「うん? それは考えなかったな」
よし、なんとか話題をそらせたみたいだ。
「この村には迷信というか、昔から語り次がれている話があるんだ。村の娘は偶然訪れてきた男性と生涯を幸せに過ごすというね。私の両親もそうだったらしい、今は二人きりで世界旅行を楽しんでいる」
「へー、なんだかロマンチックな話ですね」
「そうだ、君も偶然訪れてきた男性だな。ということは秋音を幸せにしてもらえるのか?」
「い、いや。そういう事はとくに」
「駄目なのか? 秋音の器量は悪くはないと思うんだが……」
確かに秋音は可愛い。俺が前居た学校の同級生全員と比べてもトップに位置するかもしれない。でもいきなりそんなこと言われても……。
「まぁまぁ修野君も困っているじゃないか、そのくらいで止めておいてあげようよ。秋音と修野君が仲が良いのはもう見ればわかることだし、後は当人達に任せようよ」
「幸せにしてくれる?」
秋音まで会話に参加して来た。
「しらんしらん!」
「幸せ前借りー」
「あ、おい!俺のポテトサラダ!」
「おいしいねー、おかあさんのは最高だねー」
最初の静けさは何処に行ったのか。今はもう嵐の真っ只中、無法地帯だ。
「うん、皆食べ終わったみたいだね。ごちそうさまでした」
俊夫さんの号令とともに皆ごちそうさまと言い、つつがなく昼食終了。さてこれからどうするか……
「む、まだカレーが残っているんだが」
空音さんの声に振り返ると、椅子から腰を浮かせた俊夫さんが固まっている。
「あ、あぁそうだね、それじゃおかわりもらおうかなー。あははは」
「そうか! それじゃよそってくるからな!」
満面の笑みを浮かべた空音さんと、俺の方を向いて力なく笑う俊夫さん。
「ほらねー、おとうさんいつもいっぱい食べるんだよ?」
「そういうことね……」
#
「めつぶし」
「だぁっ!!!!!!」
いきなりまぶたの上から眼球をぐりぐり押される感触、いいようのない危機感に飛び起きた俺の横にはパジャマ姿の秋音がいた。
「いきなり何すんだよ!」
「めつぶしマッサージバージョン」
「マッサージって言葉に隠れてはいるが、めつぶしにかわりはないな」
「気持ちよさそうに寝ていたから追撃しようかと。もう夜だよ?」
「うゎ、昼寝が本格的になっちまったか」
昼食後に借り家に戻った俺は、外から聞こえてくる単調な雨音と静けさからくる睡魔により昼寝を始めたワケだ。
顔に手をあてるとくっきりと畳の跡が。本気で寝ちまったみたいだ。
「シューヤずっと寝てたから起こさなかったけど、晩ご飯は残しておいたよ」
「その残りは俺が食っておいたぞ」
「オヤジ帰ってたのか……って勝手に食うなよ!」
「空音さんが作ってくれた物を見過ごすわけにはいかないからな。起きてなかった御前の負けだ」
部屋の前を通りがかったオヤジはそう言い捨てると自分の部屋へと向かっていった。
「そんなにおなかへってるの?」
「いや、ずっと寝てたから腹はへってないけどさ」
「それじゃあこれを」
秋音がポケットから取り出したのは一枚のレモンガム。
確かに腹は減ってないが一夜をガムで凌げと。
「明日の準備はした?」
「準備っていってもなぁ。とりあえず筆記用具とノートさえ持っ!!」
パン!! と大きな音をたてて俺の鼻先でクラッカーを鳴らす秋音。何処から出した!?
「ふっふっふ、心の準備はできてないみたいだねぇ」
「いきなりそんなもん鳴らされたら誰だってびっくりするわ! そんなもん持ってくるな!」
「……」
「……なんだよ、いきなり黙って」
「んーん、何でもない。それじゃおやすみなさい」
そういって部屋から出ていく秋音。廊下に出て顔だけ俺に向けてこう言った。
「入学、おめでとう」
「あ、あぁ」
俺の半端な返事が聞こえたかどうか、笑顔を見せ小さくじゃあねと言って秋音は部屋に戻っていった。
そういう事ならもっと普通に言えよ……クラッカーの残骸を片づけながら俺は心底そう思った。
#
雨音に目を覚ます。
時計を見るとまだ五時。しかし昨日昼寝をしてしまったためか二度寝をするほどの眠気は感じられない。
携帯型の小さいテレビを付け今日の天気をチェックする。
「今日の天気は一日中雨、これで二十日間連続の雨になります。早く太陽の光が見たいですね」
確かに見たいもんだ、初登校の日くらい晴れてほしかった。
準備は終わってるし、テレビもニュースくらいしかやってないし、どうするか。
思案していると腹が鳴った。そういえば昨日の昼から何も食べてない。いや、秋音がくれたレモンガムは食べたか。
今から秋音の家に向かうといっても……まだ誰も起きてないだろうし、迷惑かけるよな。
「起きてるー?」
「秋音か? お前起きるの早いな」
障子を開けて秋音が顔を出す。
まだパジャマ姿だが顔は洗ったのか、いつもと変わらない顔つきだ。
腰より少し上まである髪はまだ手入れをしていないようだが、雨露を受けた葉のような質感。これは空音さんからの遺伝なのか?
「このくらいに起きないと準備できないよ? 朝のバスは七時しかないしね」
「今まで住んでいた場所とは生活時間から違うな。明日から毎日この時間か」
「そこは任せてもらって大丈夫。あの手この手で起こしてあげるから」
「すっげぇ不安なんだけど」
「シューヤを粉骨砕身にするよー」
「意味違うだろ……」
今日は起きられたからいいが、毎日この時間に起きなければいけないと思うと少し気が滅入る。
とはいえ、目覚ましをかけずとも秋音が起こしてくれるとなれば遅刻はないだろう。もちろん自分で起きるつもりではあるが。
「ごはんできてるよ」
「あぁ、着替えてから行くよ。先に行っててくれ」
「それは考えものですなぁ」
右目だけつぶり人差し指を横に振りながら秋音はそう言う。
「もし服にお醤油とかこぼしちゃったらどうするの? また着替えなきゃいけないよね。という事は着替えずにごはんを食べるのが正解なのさー。お母さんが教えてくれたんだよ」
「それは空音さんが自分の仕事を減らしたかったからじゃ」
「あ、あれ?」
「俺は秋音と違ってこぼしたりしないぞ。秋音、空音さんに信頼されるように頑張れよ」
「わかりましたぁ……」
少し背筋を丸め悲壮感を漂わせながら秋音は部屋を出て行った。
ハンガーにかけておいた制服を着て玄関へ。大きめの傘を選び靴箱から長靴を出す。この年で長靴というのは少し恥ずかしいが、そうも言ってられないのが田舎というものだ。
舗装された道は少ししかなく、一歩外れると泥の海。ここは機能美を優先させるべきだろう。
跳ねる泥に気をつけながら歩き、正木家の玄関に着く。長靴を脱いでいると味噌汁の匂いがした。
引っ越し前は炊事掃除洗濯と全部やっていたのに、今では全部空音さんに任せてしまっている。
引っ越し初日。洗濯機を何処に置くか迷っていると空音さんが「二台一緒のほうがやりやすい」と運んでいってしまい、まず洗濯の権利を奪われた。
その夜、当然の如く俺とオヤジの分の夕食が正木家に用意されていた。
それからは何度俺がやるといっても空音さんは権利の移動を認めてくれず、結局俺が来なくともオヤジの生活はまったく問題なかったわけだ。
「空音さん、おはようございます」
「おはよう修野君」
テーブルの上にはもう朝食の準備がされていた。
席に着き頂きますと言い食べ始める。
半分ほど食べたところで秋音が入ってきた。先ほどのパジャマ姿から制服へと着替え、心なしか緊張した雰囲気をまとっている。
「秋音? 今日は制服で食べるのか。気をつけるんだぞ」
「おかあさん、頑張るよ」
頑張るような事ではないと思う。
隣に座った秋音を目の端で見ながら食事を続けていると、秋音の肘が醤油さしを小突いた。
すぐさま左手を伸ばし、間一髪で醤油さしを掴む。
「おおお」
「秋音……いきなりか」
「シューヤが居れば大丈夫だね!」
「それはどうかと思うぞ」
秋音は拍手のような動きをしている。この注意力散漫っぷりをどうにかしてもらいたい。
食事を終えて一旦家に戻る。鞄を持って庭を通り門で秋音と合流しバス停へと向かう。バス停は家のすぐそばにあり、その名前は『正木家前』である。
ほどなくして運転手以外誰も乗っていないバスが到着し、ステップで泥を落として乗り込む。
二人がけの席の窓側に座る。続いて秋音が俺の隣に座る。
「だいたい三十分くらいは乗りっぱなしだね」
「結構長いな、ひと眠りくらいできそうだ」
「そうそう! たまに眠っちゃって大変なんだよ。運転手さんに起こしてもらう時もあるし」
「迷惑かけるなって」
「大丈夫、これからはシューヤがいるから。それじゃおやすみー」
そう言った先から秋音は目を閉じ、俺の肩に寄りかかって寝息を立て始めた。これじゃ本を読む事すら出来ない。
仕方なく窓から周りの風景を見る。人の姿は見えず、時々鳥が飛んでいるだけ。コンビニなどあるはずもなく、自動販売機すらない。娯楽と言える物は何もなさそうだ。今度の休みにでも街に出て本を買い置きしておかないと。家に帰ってただ寝るだけというのはいくらなんでも駄目すぎる。
一人二人と乗って来る人が増える。その中には俺達と同じ制服を着た人間もいる。
その中の一人、秋音よりも背の小さいショートカットの女の子が俺達の方をちらちらと見ている。おそらく秋音の知り合いだろうか。俺の視線に気がついたのか彼女は軽く頭を下げた。俺も会釈を返す。
次は森家高校前とアナウンスが入った。ボタンを押して下車を伝え、秋音を揺らして起こす。熟睡していたのか目をこすりながら秋音が起きる。
「んぅ……すいません……」
「降りるぞ」
「あ、シューヤ。運転手さんかと思ったよ」
「早く立て、俺も出れないから」
バスを降りると目の前に二階建ての校舎が見える。前の高校と比べると幾分小さいが、思っていたよりはしっかりとしていた。
「秋音ちゃん、おはようございます」
俺達に遅れてバスを降りてきた先ほどの女の子が秋音に話しかける。やはり秋音の知り合いだったか。
「由佳ちゃん、おはよう。今日も寝ちゃってたよ」
「そうですね。そちらの人が前言っていた人ですか?」
「そうそう。シューヤ、自己紹介の練習しよう」
「田道修野です、よろしくお願いします」
由佳と呼ばれた女の子へ向かい、少し頭を下げて挨拶する。
「藤岡由佳です。秋音ちゃんの友達……ですよね?」
「え、えぇ? そこは確認するところなの?」
「秋音ちゃんとはこんな感じの関係です。よろしくお願いしますね」
「由佳ちゃぁん、友達だよね? ね?」
食い下がる秋音を無視し、俺に微笑みかける藤岡さん。見た目からはおとなしそうな印象を受けていたのだが、実際はしたたかな性格なのかもしれない。
「それじゃ、俺は職員室行くから」
「うん、同じクラスになれるといいねー」
「そう……かな?」
「シューヤまで!? なんかもう、今日は皆ひどいよ」
じゃあなと言い残し、秋音と藤岡さんを見送りながら職員用玄関へと回る。
傘をたたみ水滴を切りながら、いつもと変わらない鉛色の空を見上げた。降り続く雨は俺の新しい学校生活を祝福しているようには思えなかった。
#
自己紹介を簡潔に行い休み時間の質問を無難にこなすとクラスメイトの好奇心はそこで尽きたらしく、昼休みにはもうそれぞれのグループへと戻っていった。元より深い付き合いを作ろうとも思っていなかったので気にはならない。皆が昼食を取る中、食欲の無かった俺は教室を出て図書室へと向かった。
「誰も……いないな」
電気さえついていない図書室、たぶん司書もいないのだろう。
前の学校の図書室は昼休みともなると女子達が集まり大声で話をしていて、司書の人が十分ごとに止めに行くという場所だった。それと比べて、静かで本の匂いが感じられるこの図書室はとても気分が落ち着く。
最新の小説があるとは思っていなかったが、置いてある本は歴史書や図鑑などが多く、娯楽と言える本の無いこの状況は図書室の利用者を減らしている一因であることは間違いない。
それでも小説コーナーを探すと、お気に入りの作家のまだ読んでいなかった作品があった。貸出のハンコが机の上に置いてあったので勝手に押させてもらう。これで暇な時間は潰せるだろう。
制服のポケットに小説を入れようとした時、ドアを開ける音がした。視線を入り口に向けると今朝の女の子が入ってきた。
藤岡さんは俺を認識すると目を大きくさせ、驚いたような様子をみせた。
「泥棒は駄目です。そのポケットの中の物を見せなさい」
藤岡さんの声色は真剣だが、口元は少し笑っている。
「なんだ、何か証拠でもあるっていうのか?」
「ポケットの中の物が証拠です。ほら早く出しなさい」
「ほらよ」
「そうそう、このレモンガムおいしいですよね」
何気なく取り出したレモンガムを藤岡さんに渡すと、彼女は俺の顔を見据えたままガムを噛み始めた。俺の中の負けず嫌い根性が起き出し、負けじと視線を逸らさないようにする。お互いに真剣な表情だ。
そのままの姿勢で一分が過ぎたか、藤岡さんが視線を外した。
「何をやらせるんですか」
「そっちから始めた事だろ?」
「まさか田道さんがノってくるとは思いもしなかったです」
「朝もそうだったけど、藤岡さんはこういう事結構好きなのか?」
「大好きです」
藤岡さんは断言するように言った。このまま泥棒扱いされ続けても仕方が無いので、脇に挟んでいた本を広げて見せる。
「この本、ハンコを押せばいいんだよな。勝手にやっちまったけど」
「それでいいはずです。私はハンコ押さないで借りていますが」
「駄目じゃん」
「駄目ですね」
くすりと含むように笑う藤岡さん。物腰からすると良家のお嬢様といった感じなのだが中々に話しが通じて面白い人だなと思う。
「そうそう、秋音ちゃんが探してましたよ。昼ご飯一緒に食べるんだーっと言って田道さんの教室に行ったのですが」
「昼休みになってすぐにこっち来たからな……すれ違ったか」
「もしかしたら今でも探しているかもしれませんよ?」
そう藤岡さんが言った瞬間、図書室のドアが「ガン!」と音を立てて開けられた。図書室への乱入者は視線を部屋一周ぐるりとさせ、俺と藤岡さんを見つけると動きを止めた。
「えー!? なんでシューヤと由佳ちゃんが一緒にいるの!?」
秋根はずっと走り回っていたのか、少し赤くなった顔を驚きに包みながらそう言った。
「逢引です」
「逢引!? 由佳ちゃんとシューヤってもうそんな関係まで行ってるの!?」
「私と田道さんは惹かれ合う運命だったのです」
「そう言うとロマンチックだけど、その役は私のはずだよ!」
「落ち着け。何故俺が取られあう事になる」
傍目から見たら羨ましがられるような状況かもしれないが、その境遇になってみないと分からないことがあるんだな。
「突っ込み所が多すぎるぞ。役ってなんだよ」
「シューヤには期待してるよー」
「そうでしたね、田道さんは秋音ちゃんの家に来たんですからお婿さん候補ですよね」
「そーそー」
そういえば昨日の夕食で空音さんが言っていたような気がする。この村に来た人間は惹かれあう事になるとか……作り話かと思っていたが、住人ではない藤岡さんにも知られているという事は本当の話かもしれない。
「有名な話なのか? その……なんだ、村に来た人間が結婚相手とかそういうのは」
「はい。昔からの言い伝えで、この地方の人間は皆知っています。そういった話がこの周辺には多く残されていまして、本にもまとめられているくらいですよ」
「お父さんとお母さんもそうだったし、おばあちゃんとおじいちゃんもそうだったしね。間違いないよ!」
昔からの言い伝え、そして秋音の両親もその祖父祖母も同じようにしている。偶然とは言いがたいが、俺と秋音にも適用されるとなると……それは嫌だ。今の関係が言い伝えの上に成り立っているとは考えたくない。
「この本……ですね。田道さん、これも借りていきますか?」
藤岡さんは奥の本棚から一冊の古い本を取りだしてきた。おそらくこれが言い伝えの本なのだろう。
「……いいわ、今日はこの本借りたから充分だ」
「そうですか」
少しうなだれるようにして藤岡さんは残念がった。
そして昼休みの終了を告げるチャイムが鳴った。結局昼飯は食べなかったけれど腹は減っていない。これなら夕食まではもちそうだ。本をポケットに押し込み教室へと戻る。
「シューヤひどいよ、お昼ご飯食べそびれたよ」
「あー、それは悪かった」
結局秋音も俺を探す事に昼休みをさいてしまい、食べそこなったようだ。
「んー、それじゃね、放課後付き合ってくれないかな」
「別に問題ないが、何処に行くんだ?」
「それは秘密だよー」
そう言って秋音と藤岡さんは自分の教室へと戻っていった。
言い伝え……俺はそんな物信じない。
#
「ここで降りるのか?」
「そうそう、シューヤに見せてあげたい場所があるのさー」
そう言って秋音はさっさとバスを降りていってしまう。帰りを歩きと考えると三十分はかかるだろう。雨の中歩くのは大変だというのに、そこまでして見せたい物とはなんなのだろうか。
定期券をかかげながらステップを降りる。運転手もまさかここで降りるとは思わなかったのか、足元はぐずついた泥道だ。
「そこはね、ぽーんと飛ぶんだよ! 大丈夫、受け止めてあげるから」
「すまん、そこに居られると邪魔だ」
頬を膨らませながら場所を帰る秋音。少し足に力を入れて、飛ぶ。
ぱしゃっと音を立てながらも泥道を回避する事には成功した、が。
「シューヤ……泥はねた……」
そういう秋音の膝より上の部分に泥が付着していた。さすがに長靴でも隠しきれない部分だ。
「いや、その、なんだ。すまん」
「これは、汚されたと言うべきかな?」
「次はお互い気をつけような」
「了解です。それじゃ、ついて来て」
秋音は気にしたようでもなく獣道を歩いて行く。獣道と言えど、踏み固められた様子があるのでさしずめ秋音道と言った所か。
高い木に覆われた秋音道は狭く、傘をさしていると邪魔で仕方ない。木々の葉で大部分の雨粒が避けられるようなので、しまう事にする。前をみると秋音はとっくに傘をしまっていたようだ。
「なぁ、何があるんだ?」
「雨宿りだよー、ほらもう着いた!」
秋音が立ちどまった場所には周囲の木々と比べて二回りは大きい、大樹とでも言うべき木がそびえ立っていた。秋音はそのまま木のうろの中に入る。俺もそれに続き体を屈めて座りやすい根っこの上へと腰を下す。。
「この中はね、雨も入ってこないし快適なんだよ。それに、雨が降ってない時は星だって凄く綺麗なんだから」
「よくこんな場所見つけたな」
「開拓心のたまものってヤツですよ」
「実は降りるバス停間違えて、暇潰しに歩いていたら見つけたとか」
「ま、まっさかぁ」
少しどもった所から察するに、図星のようだ。
「昨日丘の上で、何もないって言ってたでしょ?」
「あぁ、確かそう言ったな」
「ここから見える星空、それだけはバッチリ保証するよ! 晴れたら来ようね!」
秋音は右手をぐっと握り、自信に満ちあふれた目で俺を見やる。この事を教える為にわざわざ連れて来てくれたのか。
「教えてくれてありがとな。でもな、場所だけ教えてくれれば俺一人で来れたって」
「いーや、それは厳しいと思うよ? 今だって私が行方をくらませばね、シューヤは家に帰る事もできずに悲しい一夜を過ごす事に……」
「マジか」
「マジだねー」
「それじゃ捕まえておくわ」
そう言いながら素早く手を伸ばし、秋音の首を後ろから掴むようにする。家に帰れなくなったら洒落にならないからな。
「私は猫じゃないんですがー」
そんな事をつぶやく秋音をうながし、元来た道を戻る。先ほどのバスまで来た所で手を放して解放してやる。
「猫使いの荒い人ですよまったく」
「お前は人だ」
「そう言うならもう猫掴みはしないでよね」
片手でシャドーボクシングをするようにして威嚇をされた。
「それじゃ帰るか。家は遠いな……」
「はりきっていきましょー」
家に帰るまでが学校と言うならば、まだまだ初日は終わらないらしい。
行程的には三十分でつけそうな距離だったが、雨を考慮に入れるのを忘れていた。結局家に着いた頃には日もほぼ落ちていた。
秋音と別れ家に入ると親父の靴があることに気づいた。今日は役所から早く帰ってこれたらしい。
部屋に着き、制服を脱ぐ。タオルを取り出して制服についた泥を払う。これをやらないとすぐに制服が痛んでしまうので、もう習慣となっている。
鞄の中身を整理するともう夕食の時間になっていた。
「オヤジ。飯の時間だぞ」
「もうこんな時間か、もう少ししたら一段落するから先行ってろ」
パソコンを睨み付けるようにしているオヤジはまだ仕事をしているようなので、言われた通り先に正木家へと向う。
台所へ向うと空音さんがちょうど料理をしている所だった。指示をもらって皿や箸の準備をする。
ほどなくして食卓が整い、俊夫さんにオヤジも来た。しかし、秋音がまだこない。
「修野君。すまないが秋音を呼んできてくれないか?」
空音さんに言われ、二階の秋音の部屋に向う。
「秋音、飯の用意できてるぞ」
ドアを叩きながら声をかけるが、少し待っても返事が無い。おそらく寝ているのだろうか。
「仕方ない……秋音! 入るぞ!」
ドアを開け、部屋の中へと入る。
案の定秋音はベッドに横になっていた。制服のままうつぶせになっていて、なんと言うか、無防備な姿である。眼鏡だけはちゃんと枕元に置いてあるのがせめてもの救いだろう。
「秋音、起きろ」
肩を掴み揺さぶるようにして起こす。
三度くらい揺らしたところで秋音は目を覚ましたようだ。腕立て伏せをするような形で起き上がり、ベッドのふちに腰を下ろす。
「おはよう……だなぁ……」
「あぁ、おはようだ。もう皆待ってるから早く来い」
「ん……ごめん……」
そういうやいなや、秋音は制服の上を巻くりあげた。条件反射的に俺は後ろを向く。
「着替えるなら俺がいなくなってからにしろ!」
「いいじゃないかー、減るもんじゃなしー」
寝ぼけているような声でそんなことを言う秋音。本当にそう思っているかどうかは疑わしいが、どちらにしても危険な状況に変わりは無い。目標である秋音を呼ぶ事を完遂した俺は後ろを向かないようにして部屋を出る。
食卓へと戻り少しすると秋音が降りてきた。全員揃ったので俊夫さんの号令で食事が始まる。
「修野、今日はどうだったんだ?」
「ああ、普通だった」
オヤジは俺の行動を根掘り葉掘り聞く事はない。俺が普通だと言ったら問題ないという事は伝わる。それが俺とオヤジの関係だと言える。
「シューヤ、それだけじゃないでしょ。シューヤには由佳ちゃんを紹介したじゃない」
「確かにそうだな。藤岡さんって言う女の子に会った」
「藤岡? そういえば今日仕事で会った人の中にも藤岡って人がいたな。娘がいるって話を聞いたぞ」
「ここら辺で藤岡っていったら由佳ちゃんの家しかないよ。たぶんそうじゃないかな」
「修野、お前も隅におけんな。藤岡さんの家はここら一帯でも有力な家だぞ? 秋音ちゃんに、その由佳って子。二股はいかんな」
「不倫はいけないよねー、おじさん」
「まったくだ」
オヤジと秋音は勝手な事を言う。こういう話に持っていかれると俺としては黙っているしかない。この二人はいいとして、むしろ空音さんと俊夫さんの反応が気になるが……。
「「修野君」」
「は、はいっ!?」
空音さんと俊夫さんが全く同じタイミングで俺に声をかけてきた。その声は丹念に砥がれ、極限まで冷やされたナイフのような雰囲気を持っていた。
「二股はいけないな。愛するならば、どちらを選ぶか決めてからにしてくれないと」
俺を見つめながら言う空音さんの顔は無表情で、その中に秘められた感情がどのような物かを推察する事は出来ない。しかし、節度の無い反応をすれば首を斬られるような雰囲気が察せられる。
「い、いや。まだそういう関係ではないので……これから考えさせてもらいます……」
「そうか、それならいい」
空音さんから発せられていた威圧感が治まった。
「それに、秋音が他の女性に負ける事などないはずだからな」
そう言って空音さんは俊夫さんを見やる。おそらく言い伝えの話を考えての発言なのだろう。
本当に、この言い伝えは浸透している。そして周囲に住んでいる人はまったくこの話を疑っていない。それは本当に効力があるからなのだろう。そして秋音も信じているのだろう、俺と結婚をすれば幸せになれると。
食事を済ませ、部屋へと戻る。寝巻きへ着替え布団に入ると、自然に考え事を始めていた。
その内容は、言い伝えの事。
この周辺の住人は盲目的に言い伝えを信じている、正木家の人もそうだ。今の関係が言い伝えからの物だとしたら……俺は嫌だ。
今まで俺は交友関係という物を作ってこなかった。オヤジの転勤が多いから友人を作らないほうが楽だ。そう思っていると自然に誰も俺には寄ってこなかった。
しかし、正木家の人達は違う。いつも通りの対応をしても近づいてきてくれる。そしてそれは何も対価を求めない自然な行為だ。俺は勝手だ。今まで求めてこなかったのに今はそれを欲しいと思っている。努力もせずに、甘えたいと思っている。
何が良い事か、何が悪い事か。そう考えていると自然に俺は眠りに落ちていった。
#
「朝だったりするよ!」
「あきね……今日は休みだぞ……」
「だからこその朝だよ!」
今日は日曜日、全国的に学校というものは休みのはずだ。それだからこそ昨夜俺は図書室で借りた本を眠たくなるまで読んでいたわけだ。それなのに、秋音はいつもと同じ時間に俺を起こしにきた。これは新手のイジメなのではあるまいか。
「今日は出かける日だからね、シューヤも用意してね」
「すまない、話の意図がまったく掴めないんだが……」
「あ、そうか。それじゃ説明を……っとその前に、ぬくやぬくや」
何がその前にかは判らないが、秋音は俺の布団に入ってくると目をつぶり温かさを満喫しはじめた。人を起こしておいてそれはないだろう。
「……二度寝していいか?」
「だ――めぇ――」
「お前だけ暖まって俺は起きろっていうのはスジが通らなくないか?」
「んー……三十分許可」
「それはありがたい。それじゃとりあえず布団から出ていけ」
丸まって本格的に寝に入ろうとしていた秋音をひっぺがすようにして追い出す。
「ぬくもりが―、ぬくませろ―」
「居間のこたつにでも入ってろ」
「了解しました―」
この貸家でもっとも気に入っているのが居間の堀ごたつだ。夏の暑い時期は流石に厳しそうだけれども、それ以外の時期はなくてはならないアイテムといっても過言ではない。
ちょうど三十分惰眠を貪り、なんとか頭も覚醒状態に持っていけたようなので着替えて居間へと向かう。
「おはようシューヤ、おせんべい食べる?」
「あー、喉渇いてるから今はいらない」
こたつの上にはせんべいの包み紙が三袋ほど落ちていた、よく朝一で食べられるものだ。秋音と反対側からこたつに潜り、足の位置を決める。
「そいでね、今日は私のお出かけの日なんだよ」
「そうか。それと俺が起こされるのには何か関係があるのか?」
「なんと言いますか、お手伝いと言いますか」
「正解は荷物持ちって所か。それと買ってくる物はクッキングペーパーとティッシュ、油も足りてなかったかな。了解した」
「うわ、先読みされた感じだよ」
少し目を大きくさせて驚く秋音。しかしせんべいを食べる口の動きは止まらずパリパリと音を立て続けている。
「買い物もそうだけど、今日はお父さんとお母さんが家でゆっくりする日だからね。私はいつも出かけているんだよ」
「家族揃ってお休みって感じじゃあないのか」
「お父さんが家にいるとね、お母さん凄いんだよ? 見ていて恥ずかしくなるっていつヤツだよ」
確かに空音さんと俊夫さんは凄く仲がいい。付き合い始めて一週間だと言われても頷けるほどのアツアツぶりと言っても過言じゃないだろう。それを見せつけられる秋音の気持ち、少し判る気がする。
「えっとね、今日は休日だからバスの時間がちょっと違うんだよ。いつもの時間から三十分後に来る感じかな。それと、たぶん朝ご飯は無いから……自分でなんとかしてもらえるかなー……」
「わかった。しかし、お前も大変だな」
「わかるー? 家族円満に見えて、その実は子供も並々ならぬ努力をしているわけですよ! 耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍んでいるわけですよ!」
「前言撤回、そこまで偉くもない。それとこぼしたせんべいは片づけてから帰れ」
箱ティッシュを投げつけ片づけさせた。
軽い食事を済ませ、時間通りにバス停へと着く。バスが走ってくるのが見えた頃になって秋音はやっと姿を見せた。バス内で言うには女性は準備に時間がかかるだの、男性は待たせるものだのと、何処で仕入れたのかそんな言い訳をされた。しかもしたり顔でだ。
それは一般論ではなくて恋愛をする上での駆け引きの一種だと教えてやると、それはそれで問題ないと親指を立てられる始末。とことんノリで生きているヤツだなと再認識をした。
少しずつ電柱が増えていく事で街に近づいている事を感じる。ある意味凄いんじゃないかと思う。買い物メモとお金は空音さんから渡されているようなので、迷う事はないだろう。
バスを降り、メモから店の場所を推測して歩き始める。
「しかしな、毎週休みの日はこうやって街まで来ているんだろ? やる事もなくなっちまうんじゃないか?」
「そうでもないよ。買い物が先だから行く場所は限られちゃうけど、本屋さんとかで充分だし」
「そうか、それじゃ俺も後で本屋行くわ」
ほどなくしてショッピングセンターに着いた。日用雑貨から床屋、服屋、本屋まで揃ったなかなかに大きな建物だ。秋音からメモを受け取り、買い物かごに物を入れていく。空音さんは俺が居る事を考慮してか、かなりの量を指定していた。会計を済ませると、大きな袋五つ分になった。
「重くはないんだけどな、凄くかさばるなコイツら」
「んー、一旦広場で落ち着こっか。それから今日の動きを決めようよ」
俺が四つ、秋音に一つ持たせて広場へと移動する。広場に居る人達は買い物客よりもカップルのほうが多く、でかいビニール袋を持った俺達は場違いに思えた。二人がけのベンチが開いていたので座り、足元に荷物を降ろす。
「はたから見たら、私とシューヤもカップルに見えますかね!」
周りを見ていた俺に対し、秋音が呼び掛けてきた。
「それはないだろ。どう見たって買い物してる兄弟にしか見えないよ」
「はっはっは、そんな事もあろうかと! カップル擬態グッズを持ってきたのですよ!」
「なんだそりゃ」
そう言って秋音は鞄から何やら取り出した。よく見て見ると、弁当箱のような……
「今日の昼ご飯です! はい拍手をどうぞー」
おざなりな拍手をしてやる。秋音は腰に手をあて胸を反らし誇らしげな様子を見せた。
早速弁当箱を開けるとおにぎりが六つに漬物と、まさにお弁当の王道といった物だった。俺としてはやれ卵焼きやらポテトサラダやら入っているものよりも、これくらいシンプルにしてあったほうが嬉しい。その点で秋音はぴったりなチョイスをしてくれたようだ。
俺が四つ、秋音が二つ食べて、弁当箱の蓋を閉める。鞄の中に入れたところで、秋音はなにやら策を含ませた顔つきで俺を見て言った。
「これでお昼ご飯代を浮かせて、本を買うわけですよ……」
「って事は、空音さんから昼飯のお金をもらってきているのか?」
「ふふ、もうシューヤは共犯ですよ? ここは折半で手を打ってはいかがでしょう」
ヌシも相当のワルよのうとでも言いそうな顔つきの秋音。しかし俺もこの提案に依存はなく、意見の一致という事で着服する事に決定した。
「今日はシューヤがいてくれたからラクだったよー」
バスを降り、屋根のある停留所のベンチに荷物を置く。
いつもはこれより少ないとはいえ、一人で買い物をするというのは大変な作業だ。それを毎週こなしていたというのだから少し感心した。
ここから家まで大きな袋を五つ運ぶ。必ず両手に袋を持たなくてはいけないので、傘をさすのもままならないだろう。どうしたものか。
「傘は私が持つから、シューヤには頑張って四つ持ってもらおう!」
確かに役割を決めたほうが運びやすいだろう。そう考えると秋音の案はとても理にかなっている。
「わかった、それじゃ傘を頼む」
「頼まれた!」
そこまで重くは無いがやたら体積をとるビニール袋を持ち上げる。そして秋音の持つ傘へと入る。
「こういう状態をなんて言うと思う?」
「あぁ?」
「ザ! あいあいがさ!」
「正しく言うなら、ジ、あいあいがさだな。英語ちゃんと勉強しろよ」
「ま、まさかの切り替えしがきたよ……」
正木家に入るとやたらツヤツヤした顔の空音さんと、笑顔ではあるが対照的に疲れ果てたような顔の俊夫さんが迎えてくれた。
玄関に荷物を置くと、空音さんは一度に全部持ち上げた。
「今日は修野君がいるから多めに頼んでしまったのだが、大丈夫だったか?」
「はい、問題なかったです」
「それは良かった。わざわざ休日を潰させてしまってすまなかった」
「大丈夫です。また何かあったら言って下さい」
空音さんはありがとうと言うと荷物を持って台所へと向っていった。秋音もその後を追う。自然と玄関に俺と俊夫さんが残る形となった。
「修野君、君はいい旦那さんになれるよ」
「そうですか?」
「秋音は家事がさっぱりでね……」
「そんな気はしてました……」
「良かったらいつか秋音に教えてやってくれ」
全てを使い果たし、後は散るのみといった雰囲気を出す俊夫さんに、俺はただうなずくことしか出来なかった。
#
それからの俺の生活はいたって普通なものだった。
毎朝秋音と共に学校へ通い、普通に授業を受け、そして帰る。部活に入っていない俺と秋音の行動はかわりばえのしない物だったが、それが楽しかった。
そしていつもの昼休み、俺と秋音と藤岡さんとの三人が集まって昼飯を食べ話をする。ここまではいつも通りだった。が、藤岡さんが持ち出した話により日常は崩れ去った。
「そう言えば、田道さんのお父さんの仕事は駄目になったみたいですね」
藤岡さんはいつものように落ちついた様子で、なんでもない事のように話し始めた。
「そうなのか? オヤジが何やっているかは知らないけど、藤岡さんのお父さんと話し合ってるとかは言ってたな」
「田道さんはお仕事の内容は知らなかったのですか!?」
「ゆ、由佳ちゃん。落ち着いて」
いつも落ち着いた様子を見せている藤岡さんとは思えない反応に俺も秋音も驚く。
「という事は、秋音ちゃんも何も知らなかったという事ですか?」
「う、うん」
「秋音ちゃんの両親も何も知らない、という事ですね?」
「そうだけど……おじさんの仕事って、なんなの?」
至極真っ当な意見だ。俺はうつむいた藤岡さんに視線を合わせ、話すように促した。
「田道さんのお父さんの仕事は……」
藤岡さんは眉をひそめ、両手で身体を抱えるようにして躊躇いを見せる。何か聞いてはいけない、聞いたら引き返せない。そんな嫌な予感だけが頭の中を駆け巡る。しかし聞かなくてはいけない。
「ダムの建設です。あの村を沈めての」
#
「それでは、田道さんはこの村をダムにする為の話し合いをしに来ていたわけですね」
家に帰るとオヤジと俊夫さんが話しをしている声が聞こえてきた。
秋音はすぐに二階へとあがり、部屋のドアを閉めた。
「そうなります」
「村の治水工事を進める為に来た、そう聞いていましたが」
オヤジと俊夫さんは応接室で向かい合うように話を進めている。俺が入り口に立っている事も気にはしない。俊夫さんの問いかけに対し深く呼吸をした後、オヤジは答えた。
「事情が変わりました。当初の計画では治水工事を行う事で村を救おうという計画でした。しかし、調査を進めるにつれて計画の遂行が困難だという結果ばかり上がってきました。長く続く雨の影響で、山はもう耐え切れなくなっています。今後数年は大丈夫でもいつ崩れるかわかりません。そしてこの村が災害に会えば違う地域にも余波が広がります」
今まで見た中で最も真剣な顔付きのオヤジ。しかし言葉にしている事はとても許容できる事ではない。
「大事の為には、小事を捨てろ。という事ですね」
「……こちらの意見は以上です。理解が得られなかったのは非常に残念ですが」
オヤジと俊夫さんの視線が交錯する。そして、俊夫さんの深い溜息とともに解ける。そのまま俊夫さんは腰を上げ、部屋を出て行った。
オヤジもまた溜息を着き、立ち上がった。俺を見る視線は力ない物だ。
「修野」
「オヤジ……」
「三日後、この村を出る。用意だけはしておけ」
それだけ言い、立ち尽くす俺の肩を叩いてオヤジは家を出て行った。
村を出る。
声に出ていた。何も考えはなく、ただその意味を確かめるかのように。
#
次の日の朝、秋音は起こしに来なかった。俺はそのまま布団に潜り続け、朝食を食べにも行かず学校も休んだ。
どうせ学校に行っても明後日には引っ越すんだ、無断欠席しても何も迷惑はかからないだろう。親父も俺に学校に行けとも言わず、おそらく何も食べずに仕事に行った。
昼になって腹が減った俺は布団を出た。居間のこたつからせんべいを取り、台所から食パンを取り、また自分の部屋へと戻った。これであと二日間過ごせるだろう。
誰もいない家で、パリパリとせんべいの音だけが響く。かなり多めに買ってきておいたのにもう数える程度にしかないのは、秋音が勝手に食べていたからだろう。
テレビを見る気もしない、本を読む気もしない、眠気もない。引っ越ししてきてから休む事なく降り続ける雨、今の俺の心境を表すにはぴったりかもしれない。
何故こんなにも空虚なのか。
何故こんなにも悲しいのか。
引っ越しだなんて今まで何度も経験してきた事じゃないか。
考えても、考えても、この心のぐらつきの原因は一つしか考えられない。それ以外の理由が出てこない。
俺は、秋音と離れるのが悲しいんだ。
家族同然の付き合い、そして今までこんなにも親しい仲になったヤツなんていなかった。
今になって気づいた。俺は秋音に対して何年も前から付き合っていたような、そんな親友以上の感覚を持っている。
だが、それももう終わる。
村をダムに沈める。知らなかったとはいえ、そんな意図で来た俺と仲良くなってしまった秋音。俺はそんな秋音が可哀想でならない。
そして俺が取るべき行動は、秋音との関係を断つ事だろう。
今までだって、引っ越す度に前の学校の事は忘れてきた。今回だって出来るはずだ。
布団に入ったままひたすら考えを続けていると、外は暗くなり夕方になった。
バスが家の前を通り過ぎる音がし、そしてパシャパシャと水を跳ねる音が微かに聞こえ、そして消えた。
秋音は学校に行き、そしていつも通りの時間に帰ってきた。それだけの事なのに、俺は少し安心した。
このまま秋音とも、空音さんとも、俊夫さんとも会わずにいよう。最後の挨拶の時に迷惑をかけました、ありがとうございましたと伝えよう。
それで、全部終わりだ。
#
次の日も俺は部屋に居た。
午前中に荷造りを済ませ、後は出るだけにした。窓を閉め切り、テレビの音を聞き流し、ただただ座っていた。
オヤジは今頃事後処理をしているはずだ。俊夫さんも空音さんも仕事に出かけ、秋音は学校で勉強しているだろう。
俺だけ何もしていない、何もする事がない。
そして日は沈み、夜が近づく。テレビの光を邪魔に感じ、電源を切り荷物の中へと押し込む。
そうした時、俺は気付いた。
雨の音がしない。
この村に来てからずっと降り続いていた雨、その音がしない。
服を着替え庭へ出て空を見上げる。そこには雲ひとつ無い星空が広がっていた。
普段は雨雲で塞がれていて見えない空。
数ヶ月ぶりに見た空は記憶の中のものとは比べ物にならないほど広く、そして綺麗だった。
そして俺は思い出した、秋音の言っていた事を。
『ここから見える星空、それだけはバッチリ保証するよ! 晴れたら来ようね!」』
その約束は守れない。こんな状態で行けるはずもない。
そう思って俺は部屋へ戻った。
部屋の時計が九時を指した頃、玄関の呼び鈴が鳴った。こんな時間に何かあったのだろうか。
玄関を開けると取り乱した様子の空音さんが立っていた。
「秋音を知らないか!? まだ帰ってきていないんだ!」
「……待っていて下さい」
俺はそれだけ言い残し、走り出した。
秋音が居る場所、それは約束した場所。それしか考えられない。
こんな時間にバスなんか走っていない。走るしかない。
雨でぬかるんだ道が邪魔をし、何度か足を取られ転びそうになる。しかし止まるわけにはいかない。秋音が待っているんだ。
#
秋音は約束の場所に居た。
少し肌寒く感じるほどの場所に、縮こまるような体勢で座っていた。
「シューヤ……」
「遅れたな」
「覚えてたんだね」
「ああ、すまなかった」
「それじゃ、なんですぐに来てくれなかったの?」
秋音の声には少し震えが混じっていた。寒さではなく、涙が混じったような声。
「……会わせる顔が無かった」
「うん」
「何も知らずに、甘えきっていた自分が許せなかった」
「うん」
「今までの事は謝っても許される事じゃない。それに、会う勇気も無かった」
「うん……」
次第に俺の声にも涙が混じり始めた。そして、頬を熱い物が伝っている事に気付いた。
「でも、シューヤは来てくれたよ。約束守ってくれたよ」
秋音がそっと俺の頬を流れる水を拭う。
「だから、許すよ。全部、全部だよ」
「星、綺麗だねぇ」
「本当だな。教えてくれてありがとな」
「どういたしましてー」
どのくらい泣いていたか解らないが、その間ずっと秋音は俺の肩を抱いていてくれた。ゆっくり身体を動かすと秋音は抱くのを止め、話しかけてきた。
本当に綺麗だった。木々の合間から見える星の光と木々の葉の露が反射する月の光。この世の物とは思えない光景。
そして、隣に座る秋音はいつもの笑顔。
しかし、他には無い最高の笑顔。
「なあ秋音」
俺はこの笑顔を失いたくない。
「なーに?」
俺はずっとこの笑顔を見ていたい。
「俺は、秋音の事が好きだ」
「私も好きだよ」
「いつになるか判らないけれど、絶対に迎えに来る」
「忘れちゃ駄目だよー?」
「絶対に忘れない」
「ほんとかなー……あまりに遅れすぎても困るよ? なんせシューヤは前科一犯だからねー」
「それを言われるとツライな……」
「そうだ、絶対に忘れない方法考えた!」
「どんなのだ?」
「今日みたいに晴れたら、絶対に空見上げるよね。あの星と……あっちの星と……その右の星、ちょうど三つで三角形になるよね。あれは私とシューヤの星座!」
「そうだな……うん、これは絶対忘れないな」
「忘れないねー」
「でもな、季節が違ったら星の場所も変わるぞ?」
「そういう時はね……」
「!?」
「こっちを……思い出してね!」
完
・水、流れる。
小高い丘の上、周りを見渡すと雄大な山並みが見える。雨を吸い込んだ地面からは強い自然の香りが発せられ、都会育ちの俺の鼻を強く刺激する。
「何もないな……」
雨が降っているのも理由の一つかもしれないが、村をぐるっと見渡しても人が歩いている様子はない。それどころか自動車さえも走っていない。
「そんなことないよー」
隣で傘をさした秋音が言う。
「本屋もないしコンビニもない……何があるんだ?」
「静けさなら、あるよ?」
「それを何もないと言うんだ」
何か変なこと言ったかなと主張するように首をかしげる秋音。雨粒がかかったのかぐしぐしと眼鏡をぬぐい、それとともにYシャツの赤いネクタイがゆれる。
「静けさに関係する話なんだけど、今夜はカレーらしいよ?」
「どこにも関係ないな」
「カレー食べるとみんな静まるよ?」
「もともと食事中はしゃべらないもんだ」
「えー、おしゃべりは楽しいのに」
どこかずれている会話。最初に会った時はめんくらったが、もう慣れた。そして村には何もないことがわかった。
「もういいわ。案内ありがとな」
「どういたしまして。それじゃカレー食べに行こう!」
そういって秋音は身をひるがえし、下り道へと足を進めはじめる。赤いスカートが揺れ、ひとつに束ねた髪がぽんぽんはねている。少し歩みを早め、秋音に追いつく。
「とりあえず、だ。まだ昼なんだが」
「昼もカレーだよ?」
「夜は昼の残りってことか……」
「違う違う。夜は夜で作るよ? 皆カレー好きだからねー。お父さんは三杯はいくね!」
「秋音はどのくらいよ?」
「福神漬けなら一パックいけるね! シューヤもどう?」
「俺はそんなにいらないな」
田道修野(たみちしゅうや)、田舎っぽいとよく言われる俺の名前。
正木秋音(まさきあきね)、目の前の少女の名前。年は同じだが、言動から考えると二、三歳下としてもだれも疑わないだろう。
「明日から一日中一緒だねぇ」
「その表現はどうかと思うが、学校案内頼むぞ」
明日から秋音と同じ学校に行く事になる。引っ越しして一番の問題がやはりクラスに溶け込めるかどうかだ。
秋音がいるから溶け込むのも楽かもしれない。
「カレーなくなるよー」
少し考えていたら秋音から離れてしまっていた。全く、どれだけ食べるんだか……。
#
丘を降りるとそこには大きな家が二件。
それは両方とも正木家の家だが、片方は俺とオヤジが貸してもらって住んでいる。
オヤジの名前は田道功治(こうじ)。公務員で一応偉い役職についているらしく、この村の開発に関しての話し合いのため俺と一緒に引っ越してきた。
俺一人残ってもよかったのだけれど、仕事はできても家事はさっぱりの父親を一人暮らしにさせるのはどうかと思いついてきた。
特に親しい友人もいなかったから未練は全くなかった。
買い物に行くのにバスで一時間はさすがにキツイけれど。
「おぉ修野、戻ったか。秋音ちゃんもおかえり。俺は話し合いにいってくるからな」
玄関から家に入ると、ちょうど傘を持ったオヤジが家をでるところだった。
「昼飯は食べたか? 秋音が言うにはカレーらしいけど」
「それが相手先の家の昼食に呼ばれていてな、本音を言えば空音さんのカレーはぜひとも食べたかったんだが……」
「空音さんは既婚者だぞ? 狙っても無駄だ」
「あんなに料理がうまくて綺麗な人はそういないぞ? 空音さんが独身だったら俺は絶対お付き合いを申し込んでいたな」
「秋音もいるんだから、滅多な事言うな」
「はっはっは、もちろん冗談だ。おしどり夫婦って言うのか? あんなのを見せつけられちゃ俺の出番はない。そうそう、秋音ちゃんだってもう少ししたら空音さんみたいに綺麗になるんじゃないか? 修野、ツバつけとくなら今のうちだぞ」
「ほっほー、じゃあ私もシューヤにつーばつーけたー」
「うわ! きたねーな! やめろって!」
秋音が自分の指を舐め頬に押し付けてくるのをブロックする。
「それじゃ行ってくる」
「あぁ、いってらっしゃい」
「またねーおじさーん」
「早くお父さんと呼んでくれるようになるのを願ってるよ」
「オヤジ! さっさといけって!」
手を上下に振り追い払う。一旦調子に乗ると止まらないのがオヤジの悪い癖だ。
「お父さんって呼ぶとおじさん喜ぶの?」
「……知らん」
「じゃあ帰ってきたら呼んでみるね!」
「それはやめろ、またややこしくなる。あーカレーの匂いがするな、早く行かないと無くなるぞ?」
シューの話は脱線することが多いし、空音さん達も待っている。俺もそろそろカレーが恋しくなってきたから話を打ち切ろう。
「そーだね、早く行かないと無くなるかもね。お父さん、中に入ろ?」
「な、何言ってんだよ! お父さんとか呼ぶな!」
「あれー、怒られたよ。おじさんの予行練習だったのに」
「……そうだ、怒られるから言うのはやめろ。な?」
「了解しましたー」
まったく、いきなりお父さんとか呼ぶなっての……意味が判ってないだけまだいいけどな。
#
靴を脱いであがり、秋音はまっすぐ台所へ。俺は何も言わずに洗面所へ。
うがい手洗いとすませたところに秋音がやってくる。
「うがい手洗いやってこいって……お母さんはひどいね、目の前にカレー置いてから言うんだよ?」
「秋音が悪い、ちゃっちゃとすませろ」
「私の分もやってよ、丘に登って疲れたよ」
「できるか。って髪濡れてるぞ」
「傘に穴が空いててびっくりしたよ。途中で枝に引っ掛けたとき壊れたのかな?」
「髪を拭くのも追加だ。さっさとしないと俺がカレー食っちまうぞ」
「食べ物の恨みはこわいよ? 報復がいやなら私が手を洗う間に髪拭いて!」
「まだ何もしてないっての……」
仕方なく置いてあったタオルを取り、がしがしと髪を拭く。
「おらおらおら!」
「乱暴にしないでよー」
「修野君、娘に乱暴は駄目だよ?」
いきなり俺たちの背後から現れたのは秋音の父親の俊夫(としお)さん。
これはやばいところを見られたかも……。
「これは乱暴を働いたわけじゃなくてですね、秋音に頼まれてやった事で」
「おとうさん、これは合意の上での行為ってやつですよ」
「違うわ!」
「合意の上ではないとなると、やはり無理やりだったんだね?」
「いや、もう、かんべんして下さい……」
俊夫さんは詰問口調ではなく少し笑い顔、秋音に乗っかって面白がっているだけだ。敗北宣言しないかぎりいくらでも攻められるだろう。
「ほい、手洗い完了だよー」
「もう髪も大丈夫だろ。全く、自分の髪くらい自分で拭けっての」
「修野君は秋音と仲が良いねぇ、僕だって秋音の髪を拭いたことないのに」
「仲が悪いとは言いませんけど、振り回されているだけのような気がします」
「今日は私が振り回される番だったけどねー」
「うらやましい限りだよ。まるで昔の僕とクーを見ているみたいだ」
そういって遠くを見るような仕草をする俊夫さん。
「空音さんと秋音じゃ全然違いますよ」
「それがそうでもないんだよね……まぁそういう話はおいおいしてあげるよ。空音が待ってるし先に行ってて」
「楽しみにしてますね。それじゃ秋音行くぞ」
「はいはいー」
#
居間に入ると食卓には人数分のカレーとポテトサラダが並べられていて、空音さんはもう席についていた。
「すいませんお待たせしました」
「それは構わない、夫もまだ来てないしな。ちゃんと食べる前には手洗いうがいをやってもらわないと、病気でもしたらたまらないからな」
「はぁ……」
この親にして、この子ありといったところか。納得。
「待たせたね、それじゃ頂こうか。いただきます」
俊夫さんに続いて皆いただきますと言い昼食が始まる。
向かって正面に俊夫さん、俺の左に秋音、左正面に空音さんという座席だ。
しばし無言でスプーンと食器がぶつかる音だけ聞こえる。この時ばかりは秋音も何もしゃべらない。
少したって腹の虫も落ち着いたのか、秋音が口を開いた。
「おかあさん、今日はシューヤを丘の上に案内してきたよ」
「ふむ、修野君は村を見てどんな感想を抱いた?」
「そうですね……何もないなぁと。空音さんはずっとこの村に住んでいるんですか?」
「あぁそうだ」
「えっと……とすると、俊夫さんとはどうやって知り合ったんですか?」
「それは僕が説明するよ」
そう言ってスプーンを置く俊夫さん。
「僕がこの村に来たのは本当に偶然だったんだ」
少しはにかみながら話を続ける。
「恥ずかしながら大学生時代に傷心旅行をやっていてね、行くあてもないバイク一人旅さ。快調にとばしていたんだけれど、ちょうどこの家の目の前でスリップして電柱に激突してしまったんだ」
「あの時は凄い音がしたからな、雷が落ちたのかと思ったぞ」
「それで空音に助けてもらって、うん、まぁいろいろあったんだよ」
「君が泣きやむまでずっと頭を撫でてやっていたな……あの夜は忘れられない……」
「い、今言うことじゃないだろ!?」
「何を言う、大切な思い出だ。今でも鮮明に思い出せるぞ? そうあの日は……」
空音さんが独演会を開こうとした時、俺は俊夫さんからの(タスケテ)というコールを受信した。
「えーと! 空音さんはずっと村に居て俊夫さんがこなかったらとか考えませんでしたか?」
「うん? それは考えなかったな」
よし、なんとか話題をそらせたみたいだ。
「この村には迷信というか、昔から語り次がれている話があるんだ。村の娘は偶然訪れてきた男性と生涯を幸せに過ごすというね。私の両親もそうだったらしい、今は二人きりで世界旅行を楽しんでいる」
「へー、なんだかロマンチックな話ですね」
「そうだ、君も偶然訪れてきた男性だな。ということは秋音を幸せにしてもらえるのか?」
「い、いや。そういう事はとくに」
「駄目なのか? 秋音の器量は悪くはないと思うんだが……」
確かに秋音は可愛い。俺が前居た学校の同級生全員と比べてもトップに位置するかもしれない。でもいきなりそんなこと言われても……。
「まぁまぁ修野君も困っているじゃないか、そのくらいで止めておいてあげようよ。秋音と修野君が仲が良いのはもう見ればわかることだし、後は当人達に任せようよ」
「幸せにしてくれる?」
秋音まで会話に参加して来た。
「しらんしらん!」
「幸せ前借りー」
「あ、おい!俺のポテトサラダ!」
「おいしいねー、おかあさんのは最高だねー」
最初の静けさは何処に行ったのか。今はもう嵐の真っ只中、無法地帯だ。
「うん、皆食べ終わったみたいだね。ごちそうさまでした」
俊夫さんの号令とともに皆ごちそうさまと言い、つつがなく昼食終了。さてこれからどうするか……
「む、まだカレーが残っているんだが」
空音さんの声に振り返ると、椅子から腰を浮かせた俊夫さんが固まっている。
「あ、あぁそうだね、それじゃおかわりもらおうかなー。あははは」
「そうか! それじゃよそってくるからな!」
満面の笑みを浮かべた空音さんと、俺の方を向いて力なく笑う俊夫さん。
「ほらねー、おとうさんいつもいっぱい食べるんだよ?」
「そういうことね……」
#
「めつぶし」
「だぁっ!!!!!!」
いきなりまぶたの上から眼球をぐりぐり押される感触、いいようのない危機感に飛び起きた俺の横にはパジャマ姿の秋音がいた。
「いきなり何すんだよ!」
「めつぶしマッサージバージョン」
「マッサージって言葉に隠れてはいるが、めつぶしにかわりはないな」
「気持ちよさそうに寝ていたから追撃しようかと。もう夜だよ?」
「うゎ、昼寝が本格的になっちまったか」
昼食後に借り家に戻った俺は、外から聞こえてくる単調な雨音と静けさからくる睡魔により昼寝を始めたワケだ。
顔に手をあてるとくっきりと畳の跡が。本気で寝ちまったみたいだ。
「シューヤずっと寝てたから起こさなかったけど、晩ご飯は残しておいたよ」
「その残りは俺が食っておいたぞ」
「オヤジ帰ってたのか……って勝手に食うなよ!」
「空音さんが作ってくれた物を見過ごすわけにはいかないからな。起きてなかった御前の負けだ」
部屋の前を通りがかったオヤジはそう言い捨てると自分の部屋へと向かっていった。
「そんなにおなかへってるの?」
「いや、ずっと寝てたから腹はへってないけどさ」
「それじゃあこれを」
秋音がポケットから取り出したのは一枚のレモンガム。
確かに腹は減ってないが一夜をガムで凌げと。
「明日の準備はした?」
「準備っていってもなぁ。とりあえず筆記用具とノートさえ持っ!!」
パン!! と大きな音をたてて俺の鼻先でクラッカーを鳴らす秋音。何処から出した!?
「ふっふっふ、心の準備はできてないみたいだねぇ」
「いきなりそんなもん鳴らされたら誰だってびっくりするわ! そんなもん持ってくるな!」
「……」
「……なんだよ、いきなり黙って」
「んーん、何でもない。それじゃおやすみなさい」
そういって部屋から出ていく秋音。廊下に出て顔だけ俺に向けてこう言った。
「入学、おめでとう」
「あ、あぁ」
俺の半端な返事が聞こえたかどうか、笑顔を見せ小さくじゃあねと言って秋音は部屋に戻っていった。
そういう事ならもっと普通に言えよ……クラッカーの残骸を片づけながら俺は心底そう思った。
#
雨音に目を覚ます。
時計を見るとまだ五時。しかし昨日昼寝をしてしまったためか二度寝をするほどの眠気は感じられない。
携帯型の小さいテレビを付け今日の天気をチェックする。
「今日の天気は一日中雨、これで二十日間連続の雨になります。早く太陽の光が見たいですね」
確かに見たいもんだ、初登校の日くらい晴れてほしかった。
準備は終わってるし、テレビもニュースくらいしかやってないし、どうするか。
思案していると腹が鳴った。そういえば昨日の昼から何も食べてない。いや、秋音がくれたレモンガムは食べたか。
今から秋音の家に向かうといっても……まだ誰も起きてないだろうし、迷惑かけるよな。
「起きてるー?」
「秋音か? お前起きるの早いな」
障子を開けて秋音が顔を出す。
まだパジャマ姿だが顔は洗ったのか、いつもと変わらない顔つきだ。
腰より少し上まである髪はまだ手入れをしていないようだが、雨露を受けた葉のような質感。これは空音さんからの遺伝なのか?
「このくらいに起きないと準備できないよ? 朝のバスは七時しかないしね」
「今まで住んでいた場所とは生活時間から違うな。明日から毎日この時間か」
「そこは任せてもらって大丈夫。あの手この手で起こしてあげるから」
「すっげぇ不安なんだけど」
「シューヤを粉骨砕身にするよー」
「意味違うだろ……」
今日は起きられたからいいが、毎日この時間に起きなければいけないと思うと少し気が滅入る。
とはいえ、目覚ましをかけずとも秋音が起こしてくれるとなれば遅刻はないだろう。もちろん自分で起きるつもりではあるが。
「ごはんできてるよ」
「あぁ、着替えてから行くよ。先に行っててくれ」
「それは考えものですなぁ」
右目だけつぶり人差し指を横に振りながら秋音はそう言う。
「もし服にお醤油とかこぼしちゃったらどうするの? また着替えなきゃいけないよね。という事は着替えずにごはんを食べるのが正解なのさー。お母さんが教えてくれたんだよ」
「それは空音さんが自分の仕事を減らしたかったからじゃ」
「あ、あれ?」
「俺は秋音と違ってこぼしたりしないぞ。秋音、空音さんに信頼されるように頑張れよ」
「わかりましたぁ……」
少し背筋を丸め悲壮感を漂わせながら秋音は部屋を出て行った。
ハンガーにかけておいた制服を着て玄関へ。大きめの傘を選び靴箱から長靴を出す。この年で長靴というのは少し恥ずかしいが、そうも言ってられないのが田舎というものだ。
舗装された道は少ししかなく、一歩外れると泥の海。ここは機能美を優先させるべきだろう。
跳ねる泥に気をつけながら歩き、正木家の玄関に着く。長靴を脱いでいると味噌汁の匂いがした。
引っ越し前は炊事掃除洗濯と全部やっていたのに、今では全部空音さんに任せてしまっている。
引っ越し初日。洗濯機を何処に置くか迷っていると空音さんが「二台一緒のほうがやりやすい」と運んでいってしまい、まず洗濯の権利を奪われた。
その夜、当然の如く俺とオヤジの分の夕食が正木家に用意されていた。
それからは何度俺がやるといっても空音さんは権利の移動を認めてくれず、結局俺が来なくともオヤジの生活はまったく問題なかったわけだ。
「空音さん、おはようございます」
「おはよう修野君」
テーブルの上にはもう朝食の準備がされていた。
席に着き頂きますと言い食べ始める。
半分ほど食べたところで秋音が入ってきた。先ほどのパジャマ姿から制服へと着替え、心なしか緊張した雰囲気をまとっている。
「秋音? 今日は制服で食べるのか。気をつけるんだぞ」
「おかあさん、頑張るよ」
頑張るような事ではないと思う。
隣に座った秋音を目の端で見ながら食事を続けていると、秋音の肘が醤油さしを小突いた。
すぐさま左手を伸ばし、間一髪で醤油さしを掴む。
「おおお」
「秋音……いきなりか」
「シューヤが居れば大丈夫だね!」
「それはどうかと思うぞ」
秋音は拍手のような動きをしている。この注意力散漫っぷりをどうにかしてもらいたい。
食事を終えて一旦家に戻る。鞄を持って庭を通り門で秋音と合流しバス停へと向かう。バス停は家のすぐそばにあり、その名前は『正木家前』である。
ほどなくして運転手以外誰も乗っていないバスが到着し、ステップで泥を落として乗り込む。
二人がけの席の窓側に座る。続いて秋音が俺の隣に座る。
「だいたい三十分くらいは乗りっぱなしだね」
「結構長いな、ひと眠りくらいできそうだ」
「そうそう! たまに眠っちゃって大変なんだよ。運転手さんに起こしてもらう時もあるし」
「迷惑かけるなって」
「大丈夫、これからはシューヤがいるから。それじゃおやすみー」
そう言った先から秋音は目を閉じ、俺の肩に寄りかかって寝息を立て始めた。これじゃ本を読む事すら出来ない。
仕方なく窓から周りの風景を見る。人の姿は見えず、時々鳥が飛んでいるだけ。コンビニなどあるはずもなく、自動販売機すらない。娯楽と言える物は何もなさそうだ。今度の休みにでも街に出て本を買い置きしておかないと。家に帰ってただ寝るだけというのはいくらなんでも駄目すぎる。
一人二人と乗って来る人が増える。その中には俺達と同じ制服を着た人間もいる。
その中の一人、秋音よりも背の小さいショートカットの女の子が俺達の方をちらちらと見ている。おそらく秋音の知り合いだろうか。俺の視線に気がついたのか彼女は軽く頭を下げた。俺も会釈を返す。
次は森家高校前とアナウンスが入った。ボタンを押して下車を伝え、秋音を揺らして起こす。熟睡していたのか目をこすりながら秋音が起きる。
「んぅ……すいません……」
「降りるぞ」
「あ、シューヤ。運転手さんかと思ったよ」
「早く立て、俺も出れないから」
バスを降りると目の前に二階建ての校舎が見える。前の高校と比べると幾分小さいが、思っていたよりはしっかりとしていた。
「秋音ちゃん、おはようございます」
俺達に遅れてバスを降りてきた先ほどの女の子が秋音に話しかける。やはり秋音の知り合いだったか。
「由佳ちゃん、おはよう。今日も寝ちゃってたよ」
「そうですね。そちらの人が前言っていた人ですか?」
「そうそう。シューヤ、自己紹介の練習しよう」
「田道修野です、よろしくお願いします」
由佳と呼ばれた女の子へ向かい、少し頭を下げて挨拶する。
「藤岡由佳です。秋音ちゃんの友達……ですよね?」
「え、えぇ? そこは確認するところなの?」
「秋音ちゃんとはこんな感じの関係です。よろしくお願いしますね」
「由佳ちゃぁん、友達だよね? ね?」
食い下がる秋音を無視し、俺に微笑みかける藤岡さん。見た目からはおとなしそうな印象を受けていたのだが、実際はしたたかな性格なのかもしれない。
「それじゃ、俺は職員室行くから」
「うん、同じクラスになれるといいねー」
「そう……かな?」
「シューヤまで!? なんかもう、今日は皆ひどいよ」
じゃあなと言い残し、秋音と藤岡さんを見送りながら職員用玄関へと回る。
傘をたたみ水滴を切りながら、いつもと変わらない鉛色の空を見上げた。降り続く雨は俺の新しい学校生活を祝福しているようには思えなかった。
#
自己紹介を簡潔に行い休み時間の質問を無難にこなすとクラスメイトの好奇心はそこで尽きたらしく、昼休みにはもうそれぞれのグループへと戻っていった。元より深い付き合いを作ろうとも思っていなかったので気にはならない。皆が昼食を取る中、食欲の無かった俺は教室を出て図書室へと向かった。
「誰も……いないな」
電気さえついていない図書室、たぶん司書もいないのだろう。
前の学校の図書室は昼休みともなると女子達が集まり大声で話をしていて、司書の人が十分ごとに止めに行くという場所だった。それと比べて、静かで本の匂いが感じられるこの図書室はとても気分が落ち着く。
最新の小説があるとは思っていなかったが、置いてある本は歴史書や図鑑などが多く、娯楽と言える本の無いこの状況は図書室の利用者を減らしている一因であることは間違いない。
それでも小説コーナーを探すと、お気に入りの作家のまだ読んでいなかった作品があった。貸出のハンコが机の上に置いてあったので勝手に押させてもらう。これで暇な時間は潰せるだろう。
制服のポケットに小説を入れようとした時、ドアを開ける音がした。視線を入り口に向けると今朝の女の子が入ってきた。
藤岡さんは俺を認識すると目を大きくさせ、驚いたような様子をみせた。
「泥棒は駄目です。そのポケットの中の物を見せなさい」
藤岡さんの声色は真剣だが、口元は少し笑っている。
「なんだ、何か証拠でもあるっていうのか?」
「ポケットの中の物が証拠です。ほら早く出しなさい」
「ほらよ」
「そうそう、このレモンガムおいしいですよね」
何気なく取り出したレモンガムを藤岡さんに渡すと、彼女は俺の顔を見据えたままガムを噛み始めた。俺の中の負けず嫌い根性が起き出し、負けじと視線を逸らさないようにする。お互いに真剣な表情だ。
そのままの姿勢で一分が過ぎたか、藤岡さんが視線を外した。
「何をやらせるんですか」
「そっちから始めた事だろ?」
「まさか田道さんがノってくるとは思いもしなかったです」
「朝もそうだったけど、藤岡さんはこういう事結構好きなのか?」
「大好きです」
藤岡さんは断言するように言った。このまま泥棒扱いされ続けても仕方が無いので、脇に挟んでいた本を広げて見せる。
「この本、ハンコを押せばいいんだよな。勝手にやっちまったけど」
「それでいいはずです。私はハンコ押さないで借りていますが」
「駄目じゃん」
「駄目ですね」
くすりと含むように笑う藤岡さん。物腰からすると良家のお嬢様といった感じなのだが中々に話しが通じて面白い人だなと思う。
「そうそう、秋音ちゃんが探してましたよ。昼ご飯一緒に食べるんだーっと言って田道さんの教室に行ったのですが」
「昼休みになってすぐにこっち来たからな……すれ違ったか」
「もしかしたら今でも探しているかもしれませんよ?」
そう藤岡さんが言った瞬間、図書室のドアが「ガン!」と音を立てて開けられた。図書室への乱入者は視線を部屋一周ぐるりとさせ、俺と藤岡さんを見つけると動きを止めた。
「えー!? なんでシューヤと由佳ちゃんが一緒にいるの!?」
秋根はずっと走り回っていたのか、少し赤くなった顔を驚きに包みながらそう言った。
「逢引です」
「逢引!? 由佳ちゃんとシューヤってもうそんな関係まで行ってるの!?」
「私と田道さんは惹かれ合う運命だったのです」
「そう言うとロマンチックだけど、その役は私のはずだよ!」
「落ち着け。何故俺が取られあう事になる」
傍目から見たら羨ましがられるような状況かもしれないが、その境遇になってみないと分からないことがあるんだな。
「突っ込み所が多すぎるぞ。役ってなんだよ」
「シューヤには期待してるよー」
「そうでしたね、田道さんは秋音ちゃんの家に来たんですからお婿さん候補ですよね」
「そーそー」
そういえば昨日の夕食で空音さんが言っていたような気がする。この村に来た人間は惹かれあう事になるとか……作り話かと思っていたが、住人ではない藤岡さんにも知られているという事は本当の話かもしれない。
「有名な話なのか? その……なんだ、村に来た人間が結婚相手とかそういうのは」
「はい。昔からの言い伝えで、この地方の人間は皆知っています。そういった話がこの周辺には多く残されていまして、本にもまとめられているくらいですよ」
「お父さんとお母さんもそうだったし、おばあちゃんとおじいちゃんもそうだったしね。間違いないよ!」
昔からの言い伝え、そして秋音の両親もその祖父祖母も同じようにしている。偶然とは言いがたいが、俺と秋音にも適用されるとなると……それは嫌だ。今の関係が言い伝えの上に成り立っているとは考えたくない。
「この本……ですね。田道さん、これも借りていきますか?」
藤岡さんは奥の本棚から一冊の古い本を取りだしてきた。おそらくこれが言い伝えの本なのだろう。
「……いいわ、今日はこの本借りたから充分だ」
「そうですか」
少しうなだれるようにして藤岡さんは残念がった。
そして昼休みの終了を告げるチャイムが鳴った。結局昼飯は食べなかったけれど腹は減っていない。これなら夕食まではもちそうだ。本をポケットに押し込み教室へと戻る。
「シューヤひどいよ、お昼ご飯食べそびれたよ」
「あー、それは悪かった」
結局秋音も俺を探す事に昼休みをさいてしまい、食べそこなったようだ。
「んー、それじゃね、放課後付き合ってくれないかな」
「別に問題ないが、何処に行くんだ?」
「それは秘密だよー」
そう言って秋音と藤岡さんは自分の教室へと戻っていった。
言い伝え……俺はそんな物信じない。
#
「ここで降りるのか?」
「そうそう、シューヤに見せてあげたい場所があるのさー」
そう言って秋音はさっさとバスを降りていってしまう。帰りを歩きと考えると三十分はかかるだろう。雨の中歩くのは大変だというのに、そこまでして見せたい物とはなんなのだろうか。
定期券をかかげながらステップを降りる。運転手もまさかここで降りるとは思わなかったのか、足元はぐずついた泥道だ。
「そこはね、ぽーんと飛ぶんだよ! 大丈夫、受け止めてあげるから」
「すまん、そこに居られると邪魔だ」
頬を膨らませながら場所を帰る秋音。少し足に力を入れて、飛ぶ。
ぱしゃっと音を立てながらも泥道を回避する事には成功した、が。
「シューヤ……泥はねた……」
そういう秋音の膝より上の部分に泥が付着していた。さすがに長靴でも隠しきれない部分だ。
「いや、その、なんだ。すまん」
「これは、汚されたと言うべきかな?」
「次はお互い気をつけような」
「了解です。それじゃ、ついて来て」
秋音は気にしたようでもなく獣道を歩いて行く。獣道と言えど、踏み固められた様子があるのでさしずめ秋音道と言った所か。
高い木に覆われた秋音道は狭く、傘をさしていると邪魔で仕方ない。木々の葉で大部分の雨粒が避けられるようなので、しまう事にする。前をみると秋音はとっくに傘をしまっていたようだ。
「なぁ、何があるんだ?」
「雨宿りだよー、ほらもう着いた!」
秋音が立ちどまった場所には周囲の木々と比べて二回りは大きい、大樹とでも言うべき木がそびえ立っていた。秋音はそのまま木のうろの中に入る。俺もそれに続き体を屈めて座りやすい根っこの上へと腰を下す。。
「この中はね、雨も入ってこないし快適なんだよ。それに、雨が降ってない時は星だって凄く綺麗なんだから」
「よくこんな場所見つけたな」
「開拓心のたまものってヤツですよ」
「実は降りるバス停間違えて、暇潰しに歩いていたら見つけたとか」
「ま、まっさかぁ」
少しどもった所から察するに、図星のようだ。
「昨日丘の上で、何もないって言ってたでしょ?」
「あぁ、確かそう言ったな」
「ここから見える星空、それだけはバッチリ保証するよ! 晴れたら来ようね!」
秋音は右手をぐっと握り、自信に満ちあふれた目で俺を見やる。この事を教える為にわざわざ連れて来てくれたのか。
「教えてくれてありがとな。でもな、場所だけ教えてくれれば俺一人で来れたって」
「いーや、それは厳しいと思うよ? 今だって私が行方をくらませばね、シューヤは家に帰る事もできずに悲しい一夜を過ごす事に……」
「マジか」
「マジだねー」
「それじゃ捕まえておくわ」
そう言いながら素早く手を伸ばし、秋音の首を後ろから掴むようにする。家に帰れなくなったら洒落にならないからな。
「私は猫じゃないんですがー」
そんな事をつぶやく秋音をうながし、元来た道を戻る。先ほどのバスまで来た所で手を放して解放してやる。
「猫使いの荒い人ですよまったく」
「お前は人だ」
「そう言うならもう猫掴みはしないでよね」
片手でシャドーボクシングをするようにして威嚇をされた。
「それじゃ帰るか。家は遠いな……」
「はりきっていきましょー」
家に帰るまでが学校と言うならば、まだまだ初日は終わらないらしい。
行程的には三十分でつけそうな距離だったが、雨を考慮に入れるのを忘れていた。結局家に着いた頃には日もほぼ落ちていた。
秋音と別れ家に入ると親父の靴があることに気づいた。今日は役所から早く帰ってこれたらしい。
部屋に着き、制服を脱ぐ。タオルを取り出して制服についた泥を払う。これをやらないとすぐに制服が痛んでしまうので、もう習慣となっている。
鞄の中身を整理するともう夕食の時間になっていた。
「オヤジ。飯の時間だぞ」
「もうこんな時間か、もう少ししたら一段落するから先行ってろ」
パソコンを睨み付けるようにしているオヤジはまだ仕事をしているようなので、言われた通り先に正木家へと向う。
台所へ向うと空音さんがちょうど料理をしている所だった。指示をもらって皿や箸の準備をする。
ほどなくして食卓が整い、俊夫さんにオヤジも来た。しかし、秋音がまだこない。
「修野君。すまないが秋音を呼んできてくれないか?」
空音さんに言われ、二階の秋音の部屋に向う。
「秋音、飯の用意できてるぞ」
ドアを叩きながら声をかけるが、少し待っても返事が無い。おそらく寝ているのだろうか。
「仕方ない……秋音! 入るぞ!」
ドアを開け、部屋の中へと入る。
案の定秋音はベッドに横になっていた。制服のままうつぶせになっていて、なんと言うか、無防備な姿である。眼鏡だけはちゃんと枕元に置いてあるのがせめてもの救いだろう。
「秋音、起きろ」
肩を掴み揺さぶるようにして起こす。
三度くらい揺らしたところで秋音は目を覚ましたようだ。腕立て伏せをするような形で起き上がり、ベッドのふちに腰を下ろす。
「おはよう……だなぁ……」
「あぁ、おはようだ。もう皆待ってるから早く来い」
「ん……ごめん……」
そういうやいなや、秋音は制服の上を巻くりあげた。条件反射的に俺は後ろを向く。
「着替えるなら俺がいなくなってからにしろ!」
「いいじゃないかー、減るもんじゃなしー」
寝ぼけているような声でそんなことを言う秋音。本当にそう思っているかどうかは疑わしいが、どちらにしても危険な状況に変わりは無い。目標である秋音を呼ぶ事を完遂した俺は後ろを向かないようにして部屋を出る。
食卓へと戻り少しすると秋音が降りてきた。全員揃ったので俊夫さんの号令で食事が始まる。
「修野、今日はどうだったんだ?」
「ああ、普通だった」
オヤジは俺の行動を根掘り葉掘り聞く事はない。俺が普通だと言ったら問題ないという事は伝わる。それが俺とオヤジの関係だと言える。
「シューヤ、それだけじゃないでしょ。シューヤには由佳ちゃんを紹介したじゃない」
「確かにそうだな。藤岡さんって言う女の子に会った」
「藤岡? そういえば今日仕事で会った人の中にも藤岡って人がいたな。娘がいるって話を聞いたぞ」
「ここら辺で藤岡っていったら由佳ちゃんの家しかないよ。たぶんそうじゃないかな」
「修野、お前も隅におけんな。藤岡さんの家はここら一帯でも有力な家だぞ? 秋音ちゃんに、その由佳って子。二股はいかんな」
「不倫はいけないよねー、おじさん」
「まったくだ」
オヤジと秋音は勝手な事を言う。こういう話に持っていかれると俺としては黙っているしかない。この二人はいいとして、むしろ空音さんと俊夫さんの反応が気になるが……。
「「修野君」」
「は、はいっ!?」
空音さんと俊夫さんが全く同じタイミングで俺に声をかけてきた。その声は丹念に砥がれ、極限まで冷やされたナイフのような雰囲気を持っていた。
「二股はいけないな。愛するならば、どちらを選ぶか決めてからにしてくれないと」
俺を見つめながら言う空音さんの顔は無表情で、その中に秘められた感情がどのような物かを推察する事は出来ない。しかし、節度の無い反応をすれば首を斬られるような雰囲気が察せられる。
「い、いや。まだそういう関係ではないので……これから考えさせてもらいます……」
「そうか、それならいい」
空音さんから発せられていた威圧感が治まった。
「それに、秋音が他の女性に負ける事などないはずだからな」
そう言って空音さんは俊夫さんを見やる。おそらく言い伝えの話を考えての発言なのだろう。
本当に、この言い伝えは浸透している。そして周囲に住んでいる人はまったくこの話を疑っていない。それは本当に効力があるからなのだろう。そして秋音も信じているのだろう、俺と結婚をすれば幸せになれると。
食事を済ませ、部屋へと戻る。寝巻きへ着替え布団に入ると、自然に考え事を始めていた。
その内容は、言い伝えの事。
この周辺の住人は盲目的に言い伝えを信じている、正木家の人もそうだ。今の関係が言い伝えからの物だとしたら……俺は嫌だ。
今まで俺は交友関係という物を作ってこなかった。オヤジの転勤が多いから友人を作らないほうが楽だ。そう思っていると自然に誰も俺には寄ってこなかった。
しかし、正木家の人達は違う。いつも通りの対応をしても近づいてきてくれる。そしてそれは何も対価を求めない自然な行為だ。俺は勝手だ。今まで求めてこなかったのに今はそれを欲しいと思っている。努力もせずに、甘えたいと思っている。
何が良い事か、何が悪い事か。そう考えていると自然に俺は眠りに落ちていった。
#
「朝だったりするよ!」
「あきね……今日は休みだぞ……」
「だからこその朝だよ!」
今日は日曜日、全国的に学校というものは休みのはずだ。それだからこそ昨夜俺は図書室で借りた本を眠たくなるまで読んでいたわけだ。それなのに、秋音はいつもと同じ時間に俺を起こしにきた。これは新手のイジメなのではあるまいか。
「今日は出かける日だからね、シューヤも用意してね」
「すまない、話の意図がまったく掴めないんだが……」
「あ、そうか。それじゃ説明を……っとその前に、ぬくやぬくや」
何がその前にかは判らないが、秋音は俺の布団に入ってくると目をつぶり温かさを満喫しはじめた。人を起こしておいてそれはないだろう。
「……二度寝していいか?」
「だ――めぇ――」
「お前だけ暖まって俺は起きろっていうのはスジが通らなくないか?」
「んー……三十分許可」
「それはありがたい。それじゃとりあえず布団から出ていけ」
丸まって本格的に寝に入ろうとしていた秋音をひっぺがすようにして追い出す。
「ぬくもりが―、ぬくませろ―」
「居間のこたつにでも入ってろ」
「了解しました―」
この貸家でもっとも気に入っているのが居間の堀ごたつだ。夏の暑い時期は流石に厳しそうだけれども、それ以外の時期はなくてはならないアイテムといっても過言ではない。
ちょうど三十分惰眠を貪り、なんとか頭も覚醒状態に持っていけたようなので着替えて居間へと向かう。
「おはようシューヤ、おせんべい食べる?」
「あー、喉渇いてるから今はいらない」
こたつの上にはせんべいの包み紙が三袋ほど落ちていた、よく朝一で食べられるものだ。秋音と反対側からこたつに潜り、足の位置を決める。
「そいでね、今日は私のお出かけの日なんだよ」
「そうか。それと俺が起こされるのには何か関係があるのか?」
「なんと言いますか、お手伝いと言いますか」
「正解は荷物持ちって所か。それと買ってくる物はクッキングペーパーとティッシュ、油も足りてなかったかな。了解した」
「うわ、先読みされた感じだよ」
少し目を大きくさせて驚く秋音。しかしせんべいを食べる口の動きは止まらずパリパリと音を立て続けている。
「買い物もそうだけど、今日はお父さんとお母さんが家でゆっくりする日だからね。私はいつも出かけているんだよ」
「家族揃ってお休みって感じじゃあないのか」
「お父さんが家にいるとね、お母さん凄いんだよ? 見ていて恥ずかしくなるっていつヤツだよ」
確かに空音さんと俊夫さんは凄く仲がいい。付き合い始めて一週間だと言われても頷けるほどのアツアツぶりと言っても過言じゃないだろう。それを見せつけられる秋音の気持ち、少し判る気がする。
「えっとね、今日は休日だからバスの時間がちょっと違うんだよ。いつもの時間から三十分後に来る感じかな。それと、たぶん朝ご飯は無いから……自分でなんとかしてもらえるかなー……」
「わかった。しかし、お前も大変だな」
「わかるー? 家族円満に見えて、その実は子供も並々ならぬ努力をしているわけですよ! 耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍んでいるわけですよ!」
「前言撤回、そこまで偉くもない。それとこぼしたせんべいは片づけてから帰れ」
箱ティッシュを投げつけ片づけさせた。
軽い食事を済ませ、時間通りにバス停へと着く。バスが走ってくるのが見えた頃になって秋音はやっと姿を見せた。バス内で言うには女性は準備に時間がかかるだの、男性は待たせるものだのと、何処で仕入れたのかそんな言い訳をされた。しかもしたり顔でだ。
それは一般論ではなくて恋愛をする上での駆け引きの一種だと教えてやると、それはそれで問題ないと親指を立てられる始末。とことんノリで生きているヤツだなと再認識をした。
少しずつ電柱が増えていく事で街に近づいている事を感じる。ある意味凄いんじゃないかと思う。買い物メモとお金は空音さんから渡されているようなので、迷う事はないだろう。
バスを降り、メモから店の場所を推測して歩き始める。
「しかしな、毎週休みの日はこうやって街まで来ているんだろ? やる事もなくなっちまうんじゃないか?」
「そうでもないよ。買い物が先だから行く場所は限られちゃうけど、本屋さんとかで充分だし」
「そうか、それじゃ俺も後で本屋行くわ」
ほどなくしてショッピングセンターに着いた。日用雑貨から床屋、服屋、本屋まで揃ったなかなかに大きな建物だ。秋音からメモを受け取り、買い物かごに物を入れていく。空音さんは俺が居る事を考慮してか、かなりの量を指定していた。会計を済ませると、大きな袋五つ分になった。
「重くはないんだけどな、凄くかさばるなコイツら」
「んー、一旦広場で落ち着こっか。それから今日の動きを決めようよ」
俺が四つ、秋音に一つ持たせて広場へと移動する。広場に居る人達は買い物客よりもカップルのほうが多く、でかいビニール袋を持った俺達は場違いに思えた。二人がけのベンチが開いていたので座り、足元に荷物を降ろす。
「はたから見たら、私とシューヤもカップルに見えますかね!」
周りを見ていた俺に対し、秋音が呼び掛けてきた。
「それはないだろ。どう見たって買い物してる兄弟にしか見えないよ」
「はっはっは、そんな事もあろうかと! カップル擬態グッズを持ってきたのですよ!」
「なんだそりゃ」
そう言って秋音は鞄から何やら取り出した。よく見て見ると、弁当箱のような……
「今日の昼ご飯です! はい拍手をどうぞー」
おざなりな拍手をしてやる。秋音は腰に手をあて胸を反らし誇らしげな様子を見せた。
早速弁当箱を開けるとおにぎりが六つに漬物と、まさにお弁当の王道といった物だった。俺としてはやれ卵焼きやらポテトサラダやら入っているものよりも、これくらいシンプルにしてあったほうが嬉しい。その点で秋音はぴったりなチョイスをしてくれたようだ。
俺が四つ、秋音が二つ食べて、弁当箱の蓋を閉める。鞄の中に入れたところで、秋音はなにやら策を含ませた顔つきで俺を見て言った。
「これでお昼ご飯代を浮かせて、本を買うわけですよ……」
「って事は、空音さんから昼飯のお金をもらってきているのか?」
「ふふ、もうシューヤは共犯ですよ? ここは折半で手を打ってはいかがでしょう」
ヌシも相当のワルよのうとでも言いそうな顔つきの秋音。しかし俺もこの提案に依存はなく、意見の一致という事で着服する事に決定した。
「今日はシューヤがいてくれたからラクだったよー」
バスを降り、屋根のある停留所のベンチに荷物を置く。
いつもはこれより少ないとはいえ、一人で買い物をするというのは大変な作業だ。それを毎週こなしていたというのだから少し感心した。
ここから家まで大きな袋を五つ運ぶ。必ず両手に袋を持たなくてはいけないので、傘をさすのもままならないだろう。どうしたものか。
「傘は私が持つから、シューヤには頑張って四つ持ってもらおう!」
確かに役割を決めたほうが運びやすいだろう。そう考えると秋音の案はとても理にかなっている。
「わかった、それじゃ傘を頼む」
「頼まれた!」
そこまで重くは無いがやたら体積をとるビニール袋を持ち上げる。そして秋音の持つ傘へと入る。
「こういう状態をなんて言うと思う?」
「あぁ?」
「ザ! あいあいがさ!」
「正しく言うなら、ジ、あいあいがさだな。英語ちゃんと勉強しろよ」
「ま、まさかの切り替えしがきたよ……」
正木家に入るとやたらツヤツヤした顔の空音さんと、笑顔ではあるが対照的に疲れ果てたような顔の俊夫さんが迎えてくれた。
玄関に荷物を置くと、空音さんは一度に全部持ち上げた。
「今日は修野君がいるから多めに頼んでしまったのだが、大丈夫だったか?」
「はい、問題なかったです」
「それは良かった。わざわざ休日を潰させてしまってすまなかった」
「大丈夫です。また何かあったら言って下さい」
空音さんはありがとうと言うと荷物を持って台所へと向っていった。秋音もその後を追う。自然と玄関に俺と俊夫さんが残る形となった。
「修野君、君はいい旦那さんになれるよ」
「そうですか?」
「秋音は家事がさっぱりでね……」
「そんな気はしてました……」
「良かったらいつか秋音に教えてやってくれ」
全てを使い果たし、後は散るのみといった雰囲気を出す俊夫さんに、俺はただうなずくことしか出来なかった。
#
それからの俺の生活はいたって普通なものだった。
毎朝秋音と共に学校へ通い、普通に授業を受け、そして帰る。部活に入っていない俺と秋音の行動はかわりばえのしない物だったが、それが楽しかった。
そしていつもの昼休み、俺と秋音と藤岡さんとの三人が集まって昼飯を食べ話をする。ここまではいつも通りだった。が、藤岡さんが持ち出した話により日常は崩れ去った。
「そう言えば、田道さんのお父さんの仕事は駄目になったみたいですね」
藤岡さんはいつものように落ちついた様子で、なんでもない事のように話し始めた。
「そうなのか? オヤジが何やっているかは知らないけど、藤岡さんのお父さんと話し合ってるとかは言ってたな」
「田道さんはお仕事の内容は知らなかったのですか!?」
「ゆ、由佳ちゃん。落ち着いて」
いつも落ち着いた様子を見せている藤岡さんとは思えない反応に俺も秋音も驚く。
「という事は、秋音ちゃんも何も知らなかったという事ですか?」
「う、うん」
「秋音ちゃんの両親も何も知らない、という事ですね?」
「そうだけど……おじさんの仕事って、なんなの?」
至極真っ当な意見だ。俺はうつむいた藤岡さんに視線を合わせ、話すように促した。
「田道さんのお父さんの仕事は……」
藤岡さんは眉をひそめ、両手で身体を抱えるようにして躊躇いを見せる。何か聞いてはいけない、聞いたら引き返せない。そんな嫌な予感だけが頭の中を駆け巡る。しかし聞かなくてはいけない。
「ダムの建設です。あの村を沈めての」
#
「それでは、田道さんはこの村をダムにする為の話し合いをしに来ていたわけですね」
家に帰るとオヤジと俊夫さんが話しをしている声が聞こえてきた。
秋音はすぐに二階へとあがり、部屋のドアを閉めた。
「そうなります」
「村の治水工事を進める為に来た、そう聞いていましたが」
オヤジと俊夫さんは応接室で向かい合うように話を進めている。俺が入り口に立っている事も気にはしない。俊夫さんの問いかけに対し深く呼吸をした後、オヤジは答えた。
「事情が変わりました。当初の計画では治水工事を行う事で村を救おうという計画でした。しかし、調査を進めるにつれて計画の遂行が困難だという結果ばかり上がってきました。長く続く雨の影響で、山はもう耐え切れなくなっています。今後数年は大丈夫でもいつ崩れるかわかりません。そしてこの村が災害に会えば違う地域にも余波が広がります」
今まで見た中で最も真剣な顔付きのオヤジ。しかし言葉にしている事はとても許容できる事ではない。
「大事の為には、小事を捨てろ。という事ですね」
「……こちらの意見は以上です。理解が得られなかったのは非常に残念ですが」
オヤジと俊夫さんの視線が交錯する。そして、俊夫さんの深い溜息とともに解ける。そのまま俊夫さんは腰を上げ、部屋を出て行った。
オヤジもまた溜息を着き、立ち上がった。俺を見る視線は力ない物だ。
「修野」
「オヤジ……」
「三日後、この村を出る。用意だけはしておけ」
それだけ言い、立ち尽くす俺の肩を叩いてオヤジは家を出て行った。
村を出る。
声に出ていた。何も考えはなく、ただその意味を確かめるかのように。
#
次の日の朝、秋音は起こしに来なかった。俺はそのまま布団に潜り続け、朝食を食べにも行かず学校も休んだ。
どうせ学校に行っても明後日には引っ越すんだ、無断欠席しても何も迷惑はかからないだろう。親父も俺に学校に行けとも言わず、おそらく何も食べずに仕事に行った。
昼になって腹が減った俺は布団を出た。居間のこたつからせんべいを取り、台所から食パンを取り、また自分の部屋へと戻った。これであと二日間過ごせるだろう。
誰もいない家で、パリパリとせんべいの音だけが響く。かなり多めに買ってきておいたのにもう数える程度にしかないのは、秋音が勝手に食べていたからだろう。
テレビを見る気もしない、本を読む気もしない、眠気もない。引っ越ししてきてから休む事なく降り続ける雨、今の俺の心境を表すにはぴったりかもしれない。
何故こんなにも空虚なのか。
何故こんなにも悲しいのか。
引っ越しだなんて今まで何度も経験してきた事じゃないか。
考えても、考えても、この心のぐらつきの原因は一つしか考えられない。それ以外の理由が出てこない。
俺は、秋音と離れるのが悲しいんだ。
家族同然の付き合い、そして今までこんなにも親しい仲になったヤツなんていなかった。
今になって気づいた。俺は秋音に対して何年も前から付き合っていたような、そんな親友以上の感覚を持っている。
だが、それももう終わる。
村をダムに沈める。知らなかったとはいえ、そんな意図で来た俺と仲良くなってしまった秋音。俺はそんな秋音が可哀想でならない。
そして俺が取るべき行動は、秋音との関係を断つ事だろう。
今までだって、引っ越す度に前の学校の事は忘れてきた。今回だって出来るはずだ。
布団に入ったままひたすら考えを続けていると、外は暗くなり夕方になった。
バスが家の前を通り過ぎる音がし、そしてパシャパシャと水を跳ねる音が微かに聞こえ、そして消えた。
秋音は学校に行き、そしていつも通りの時間に帰ってきた。それだけの事なのに、俺は少し安心した。
このまま秋音とも、空音さんとも、俊夫さんとも会わずにいよう。最後の挨拶の時に迷惑をかけました、ありがとうございましたと伝えよう。
それで、全部終わりだ。
#
次の日も俺は部屋に居た。
午前中に荷造りを済ませ、後は出るだけにした。窓を閉め切り、テレビの音を聞き流し、ただただ座っていた。
オヤジは今頃事後処理をしているはずだ。俊夫さんも空音さんも仕事に出かけ、秋音は学校で勉強しているだろう。
俺だけ何もしていない、何もする事がない。
そして日は沈み、夜が近づく。テレビの光を邪魔に感じ、電源を切り荷物の中へと押し込む。
そうした時、俺は気付いた。
雨の音がしない。
この村に来てからずっと降り続いていた雨、その音がしない。
服を着替え庭へ出て空を見上げる。そこには雲ひとつ無い星空が広がっていた。
普段は雨雲で塞がれていて見えない空。
数ヶ月ぶりに見た空は記憶の中のものとは比べ物にならないほど広く、そして綺麗だった。
そして俺は思い出した、秋音の言っていた事を。
『ここから見える星空、それだけはバッチリ保証するよ! 晴れたら来ようね!」』
その約束は守れない。こんな状態で行けるはずもない。
そう思って俺は部屋へ戻った。
部屋の時計が九時を指した頃、玄関の呼び鈴が鳴った。こんな時間に何かあったのだろうか。
玄関を開けると取り乱した様子の空音さんが立っていた。
「秋音を知らないか!? まだ帰ってきていないんだ!」
「……待っていて下さい」
俺はそれだけ言い残し、走り出した。
秋音が居る場所、それは約束した場所。それしか考えられない。
こんな時間にバスなんか走っていない。走るしかない。
雨でぬかるんだ道が邪魔をし、何度か足を取られ転びそうになる。しかし止まるわけにはいかない。秋音が待っているんだ。
#
秋音は約束の場所に居た。
少し肌寒く感じるほどの場所に、縮こまるような体勢で座っていた。
「シューヤ……」
「遅れたな」
「覚えてたんだね」
「ああ、すまなかった」
「それじゃ、なんですぐに来てくれなかったの?」
秋音の声には少し震えが混じっていた。寒さではなく、涙が混じったような声。
「……会わせる顔が無かった」
「うん」
「何も知らずに、甘えきっていた自分が許せなかった」
「うん」
「今までの事は謝っても許される事じゃない。それに、会う勇気も無かった」
「うん……」
次第に俺の声にも涙が混じり始めた。そして、頬を熱い物が伝っている事に気付いた。
「でも、シューヤは来てくれたよ。約束守ってくれたよ」
秋音がそっと俺の頬を流れる水を拭う。
「だから、許すよ。全部、全部だよ」
「星、綺麗だねぇ」
「本当だな。教えてくれてありがとな」
「どういたしましてー」
どのくらい泣いていたか解らないが、その間ずっと秋音は俺の肩を抱いていてくれた。ゆっくり身体を動かすと秋音は抱くのを止め、話しかけてきた。
本当に綺麗だった。木々の合間から見える星の光と木々の葉の露が反射する月の光。この世の物とは思えない光景。
そして、隣に座る秋音はいつもの笑顔。
しかし、他には無い最高の笑顔。
「なあ秋音」
俺はこの笑顔を失いたくない。
「なーに?」
俺はずっとこの笑顔を見ていたい。
「俺は、秋音の事が好きだ」
「私も好きだよ」
「いつになるか判らないけれど、絶対に迎えに来る」
「忘れちゃ駄目だよー?」
「絶対に忘れない」
「ほんとかなー……あまりに遅れすぎても困るよ? なんせシューヤは前科一犯だからねー」
「それを言われるとツライな……」
「そうだ、絶対に忘れない方法考えた!」
「どんなのだ?」
「今日みたいに晴れたら、絶対に空見上げるよね。あの星と……あっちの星と……その右の星、ちょうど三つで三角形になるよね。あれは私とシューヤの星座!」
「そうだな……うん、これは絶対忘れないな」
「忘れないねー」
「でもな、季節が違ったら星の場所も変わるぞ?」
「そういう時はね……」
「!?」
「こっちを……思い出してね!」
完
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: