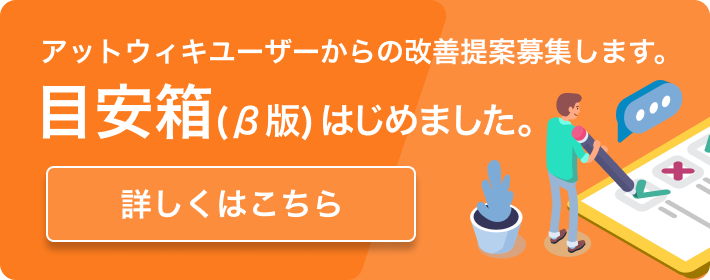「恐怖小話 その壱」(2006/06/07 (水) 08:37:55) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
*恐怖小話 その壱
身の毛もよだつ恐怖小話を2つ、お話しいたしましょう。
死ばかりを見る女
不幸を呼び寄せる人。あの人の行くところでは必ず何か不幸な事件が起こる・・・皆さんの周りにそんな人はいないだろうか。そう、例えば「じっちゃんの名にかけて」の金田一少年や「見た目は子供、頭脳は大人」名探偵コナン君、あるいは「見た目は大人、でも頭脳は子供」迷探偵桂小枝のように。そんな話、マンガの中だけだよ、現実には有り得ない、そう思っていたあなた、よくよく周りを見回してみてください。それはあなたの意外とすぐ近く、いやもしかしたらあなた自身が・・・
これは、そんな一人の女性の物語です。
「私だって、好き好んでそんな変な癖をつけたわけじゃないんです。でも私、気がついたときにはいつも・・・」
こう話してくれたのは静岡県S市在住の専業主婦、Aさん(47歳)である。Aさんがこの奇妙な事実に気がついたのは、今から20年ほど前の夏の終わり、涼しい朝のことだった。
ウィィィィン!ウィィィィン!
Aさんはどこか聞きなれた機械音で目を覚ました。どうやら隣の家から聞こえてくるようだ。そしてAさんはまるで何かに引き寄せられるように玄関を出て庭に出た。Aさんがそこで見たものは・・・
隣の家のご主人が庭の芝を刈っていたのだった。Aさんはその光景をずっとずっと、芝刈りが終わるまで眺めていた。
「それ以来、まるで何かに取り憑かれたように芝刈りを見てはうっとりする自分がいるんです。全く、どうしてこんな変な癖がついてしまったのかしら・・・」
と“芝刈りを見る女”Aさんは語る。
あなたにもこんな変な癖、ありませんか・・・?
恐怖の味噌汁
言わずと知れた和食の定番、味噌汁。ある統計によると、日本人は平均して一日にお椀一杯~二杯の頻度で味噌汁を飲むそうである。それほど味噌汁は日本人にとって馴染みの深い料理なのだ。ところが一方で、味噌汁にまつわるこぼれ恐怖話も少なくない。ここでいくつか紹介しよう。
室町~江戸時代にかけて、味噌汁が暗殺に使われることがあった。例えばある家庭で、夫に恨みを持った妻は夫の飲む味噌汁に毎日、少しずつ毒薬を混ぜておく。するとどんなに元気な人間でも数ヶ月のうちにみるみる体調が悪化し、死に至る。妻は病死にみせかけて夫を殺害することができるのだ。誰もが毎日のように味噌汁を飲むという日本人の生活習慣を巧みに利用した方法である。
また、長野県の山深いところに存在する味噌汁沼に腰上まではまる快感は「マニアにはたまらない」ともっぱらの評判である。「いやぁ、味噌汁って、本っ当に、いいもんですねぇ」こう語ってくれたのは自称業界人・M野はるおさんである。マニアというか、廃人である。
さて本題に戻ろう。これは、まだ小学校にあがったばかりの少年Nの、味噌汁にまつわる恐怖体験である。
もう夏も近いというのにこんなに寒い朝を、少年Nは生まれてから一度だって経験したことがなかった。確かにその朝は小雨がしとしとと降り、いつもと比べて冷え込んでいた。しかしそれ以上に、少年Nの心は冷えきっていた。昨晩、彼は生まれて初めて、母親と大喧嘩をした。食事中の行儀が悪い、事の発端はそんな些細なことだった。しかしそれをきっかけに、母と子は今まで溜まっていたホンネをぶちまけあった。お母さんなんて大嫌いだ、少年Nはそう思った。今朝になってもまだ怒りはおさまらず、少年はもう1時間も前から目を覚ましていたのだけれど、なかなか布団から出ようとはしなかった。
台所からは、いつものようにお母さんが朝食を作る音が聞こえる。トントントントン・・・包丁の音。人を包丁で刺したら、血がいっぱい出て死んじゃうのかなあ。少年Nの心は荒んでいた。
30分ほどたったころ、台所から母親の声。
「ごはんよー。起きなさーい」
少年はしぶしぶ台所へと向かった。お母さんの前で、どんな顔をしたらいいんだろう。まともに目を合わせたら、またふつふつと怒りが込み上げてくるかもしれないのに。
台所に入ると、おいしそうな味噌汁の匂いが、少年の鼻腔を激しく攻めたてた。そしてそこには、笑顔の母親が立っていた。
「今日はあなたの大好きな麩のお味噌汁よ。昨日はごめんなさいね、お母さん、少し言い過ぎたわ。」
「今日・・麩の味噌汁?」
少年の顔に笑顔が戻った。いつのまにか雨は上がり、あたたかい太陽が雲の谷間から顔をのぞかせていた。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: